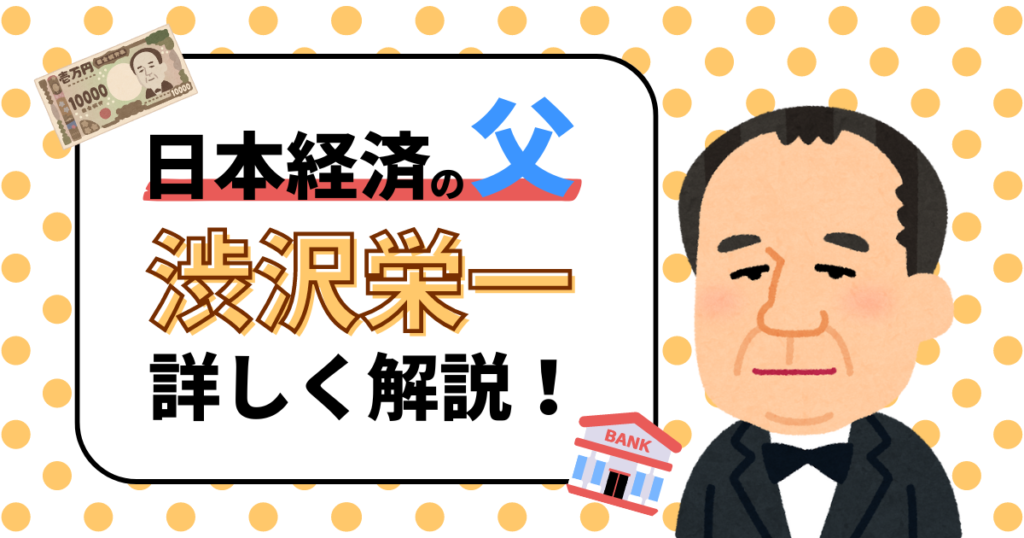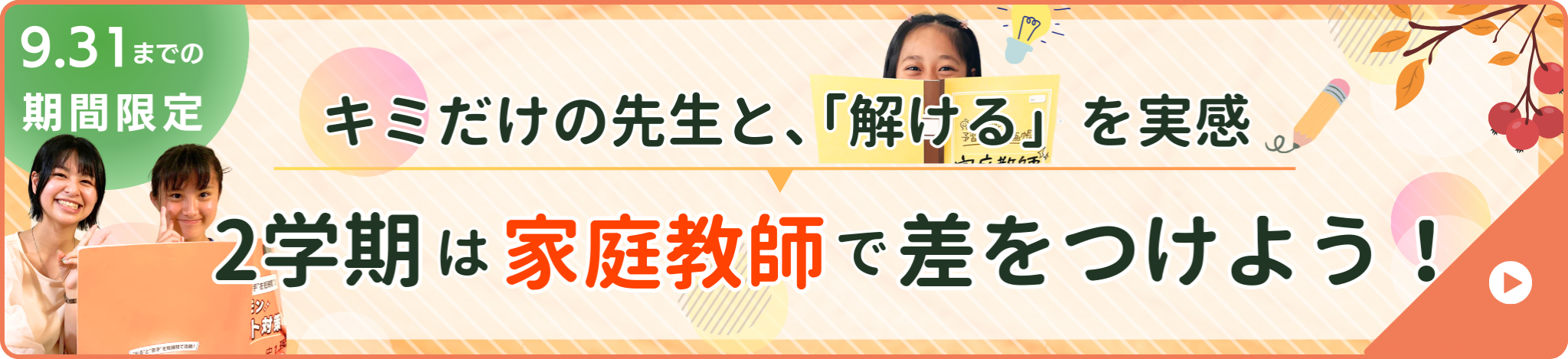





小学校低学年の宿題に「音読」が毎日ありますよね。
面倒くさい!と子供が嫌がり、音読カードに読んでもないけれど丸を付けているお母さん達、少なくないのではないでしょうか?
しかし、音読は小学生のうちに身に着けておきたい一番基礎の力である「読解力」や「表現力」を鍛えるのにとても大切なんです。
音読のメリットを一緒に確認しておきましょう!
文章の内容や意味を深く理解し、読解力を育むのに音読は効果的です。
わかる言葉を増やすし、語彙力を高めることが読解力の向上には大切です。
音読は、わかる言葉を増やすのにとても効果的です。
読解力がないと、算数の文章題を「意味が分からない。」と言ってあきらめてしまうお子さんになってしまいます。
すべて教科の基礎となる読解力を鍛えるためにも、音読の宿題はさぼらせないようにしたいですね。
音読は話すスピードや発音を理解し、他人の話す内容を正しく聞き取る力を養います。
声を出すことだけでなく耳からも自分の言葉が入ってくるので「聞く」力も必然的に伸びていきます。
読解力の向上の項目でも紹介しましたが、音読をすることで語彙力、つまり知っている言葉が増えていきます。
また、自分では知らなかった言い回しを知ることができるため、豊かな表現力や文章理解力が育まれます。
新しい言葉や表現をたくさん聞くことで、うまく自分の気持ちを表演できるようになりコミュニケーション能力がアップしていきます。
音読は私たちが思っているよりも、脳の多くの部分を刺激し、脳の活性化を促進します。
文章を目で追い、理解し、声に出すことは複数の脳領域が関わっており、脳の働きを活発にします。
毎日続けることで、脳活性化効果にも役立ちます。
なぜ、音読と記憶力が結びつくの?と疑問に思いますよね。
脳の活性化の項でも触れましたが音読は脳の中でも様々な分野を刺激しています。
2017年、カナダのウォータールー大学コリン・マクラウド心理学教授は、記憶力の研究をおこなって
「覚えなくてはならないことを声に出すと、情報を覚えるとき覚えやすい形に置き換えて取り込まれやすい」という研究結果を発表しています。
「生産効果」現象という現象らしいです。
覚えたい部分は声に出して音読すること。
そうすることで記憶に定着していきます。
こんなに効果のある音読。せっかくなら効果的に行いたいですよね。
音読を効果的に行うために気を付けるポイントをまとめました。
だらだらと読む、ぶつぶつ小声で読むのはNG!
文章をはっきりとした声で読ませましょう。発音を大切にし、言葉を明瞭に伝えることが大切です。
はっきりとした声を出すために、姿勢は大切です。
背筋を伸はし、姿勢を正しくすることで声が出しやすくなり、はっきりと発音することができるようになります。
ここまでは、子供のコツを紹介しました。
もちろん、音読の聞き手である親にも音読の効果を高めるためにできるコツがあるんです。
子供のやる気を無くすことなく続けられるように、親も工夫をしていきましょうね。
音読は意外にも時間がとられるので親からしても面倒ですよね。
しかし、ほかのことをしながら子供の音読を聞くのではなく、しっかり向き合って聞いてあげましょう。
親がしっかりと「聞く姿勢」を取ることで、子供も「相手に伝える」という目的が加わってきます。
音読を聞きながら、読み方の間違えている漢字や、意味が分かっていなさそうな単語を都度教えてあげましょう。
また、意外と子供は「読み飛ばし」が多いのです。意図的ではなかったとしても読み飛ばすことで意味が異なって文章がつながってしまうこともあります。
そういったところをしっかり伝えながら音読に取り組みましょう。
聞きながら確認すること、は決して詰まったからといって叱るということと同義ではありません。
うまくいかなくて叱られる、という経験は子どもがやる気をなくしてしまう原因の第一位です。
分からない言葉は一緒に調べてるなどして、一緒に学ぶ時間にしましょう。
「今すらすら読めなくても、今度はすらすら読めるようになってるよ!」と励ましながら進めていきましょうね。
教科書を音読している場合、何度も同じ場所を読むことになり子供が嫌がることも増えますよね。
そう言ったときには何を音読させたらいいのでしょうか?
音読は単純で、手軽に始まられますが、効果が認められている学習法の一つです。
そんな音読を取り入れようと考える方は多いのか、多くの音読本が発売されています。
一例を紹介しますね。
●頭がよくなる! 寝るまえ1分おんどく366日
脳科学者、加藤俊徳さん監修
●陰山英男の徹底反復 音読プリント
有名な教育者影山先生考案。小学4年生~高学年におすすめ
単純て手軽なのにうれしい効果がたくさんの音読。
ぜひ毎日の学習に取り入れてみてくださいね。