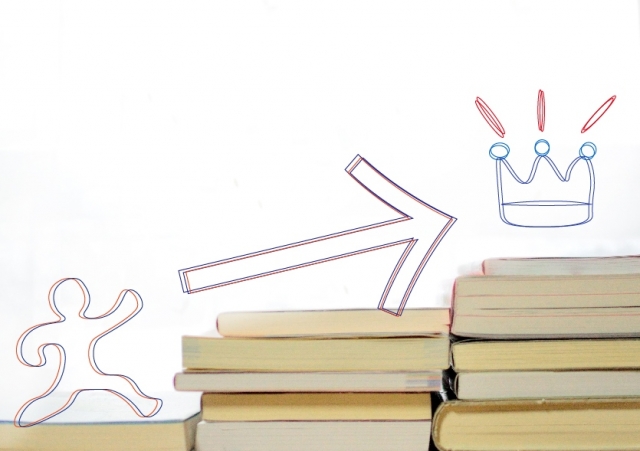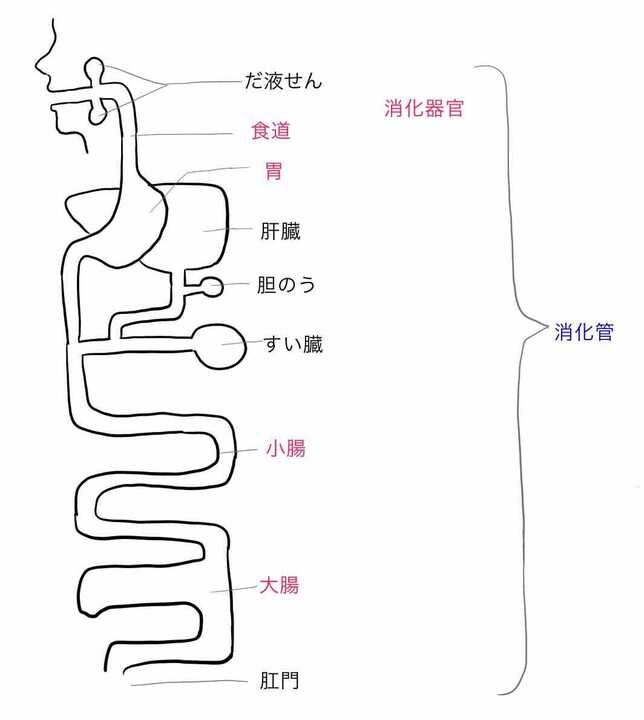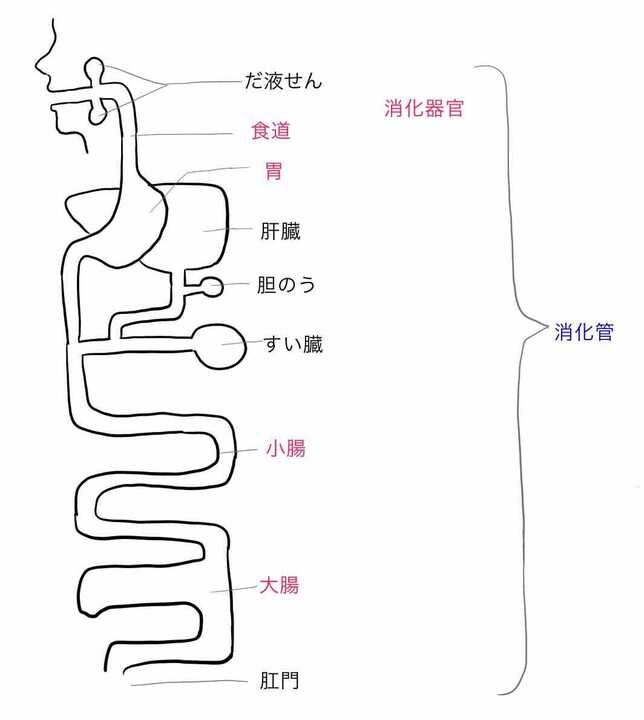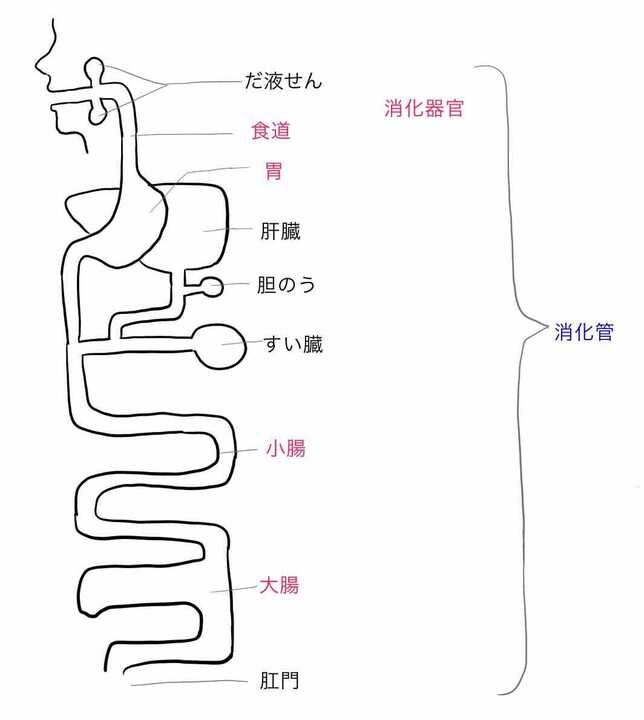前回は
について勉強していきました。
今回は
を勉強していきましょう!
特に速度の計算問題は定期テストはもちろん、入試問題にも頻出です。
ここでしっかり押さえていきましょう!
地震の大きさを表す方法として、主に2つが使われています。テレビの地震速報でもこれから紹介する2つは見たことがあると思います。
マグニチュードは地震そのものの大きさを表す単位です。数が大きくなればなるほど、より地震の規模が大きくなったことを表します。
マグニチュードが1変わると、その地震の規模は約32倍大きくなります。
| マグニチュード | 地震名 | 起こった年 |
| 9.5 | チリ地震 | 1960年 |
| 9.2 | アラスカ地震 | 1964年 |
| 9.1 | アリューシャン地震 | 1957年 |
| 9.0 | 東日本大震災 | 2011年 |
| 9.0 | スマトラ島沖地震 | 2004年 |
震度は地震の揺れの大きさを表す単位です。以下の図のように10段階で表されます。
東日本大震災の時には最大震度の7が観測されたそうです。
よく出題されますが、最低震度が0、最高震度が7なので注意してください!
| 震度 | 人の体感・行動 |
| 震度0 | 人は揺れを感じないが、地震計には記録される。 |
| 震度1 | 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。 |
| 震度2 | 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。眠っている人の中には、目を覚ます人もいる。 |
| 震度3 | 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。歩いている人の中には、揺れを感じる人もいる。眠っている人の大半が、目を覚ます。 |
| 震度4 | ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。 |
| 震度5弱 | 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 |
| 震度5強 | 大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。 |
| 震度6弱 | 立っていることが困難になる。 |
| 震度6強 | 揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 |
| 震度7 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。 |
震度は地震計が測定した揺れの大きさを元に0~7で表されます。震度7は地球の重力加速度とほぼ同じくらい大きさです。
その為、震度8を記録する揺れとなると重力加速度の6倍!の大きさを観測することになるので、実際には起こりえないだろうと言われています。
また、震度を定めているのは気象庁なので日本のみの尺度です。目的としては地震の大きさが人の体感・行動にどれほどの影響を与えるのかを客観的に定める為です。
なので、震度5と6は、地震計が同じ値を示しても人間に及ぼした被害や影響を考慮して「強と弱」のどちらかで表されるようになっているそうです。
それでは、今回のメイン:速度問題の解説をしていきたいと思います。大事になってくるポイントは大きく3つあります。
①P波とS波、初期微動継続時間をしっかり理解しておくこと。
こちらは前回の記事で詳しく載せています。不安だなぁという方はご覧ください。
②P波とS波は発生する時間は同じであるということ。
これに関しては、当然ですね。地震は発生してからPとSに分かれるので発生源は1か所です。地震が発生する場所のことを「震源」と呼びます。
③初期微動継続時間は震源からの距離に比例すること。
例えば震源からの距離が30kmの場所で初期微動継続時間が30秒だった時、距離が60kmの場所では倍の60秒になります。
ここでのポイントは震源からの距離が遠くなるほど、初期微動継続時間は長くなることです。
これもP波とS波が一定の速度で進むことを考えると当然と言えます。
それでは早速問題を見てみましょう!
ある場所で地震が発生し、震源からの距離がそれぞれ60km、120km、200kmの地点で初期微動が始まった時刻と、主要動が発生した時刻を記録したところ
60km地点では初期微動が11時00分15秒、主要動が11時00分25秒
120km地点では初期微動が11時00分25秒、主要動が11時00分45秒
240km地点では初期微動が11時00分45秒、主要動は不備があり計測が出来なかった
この時以下の問いに答えよ。
Q1.S波の速さを求めよ。
Q2.地震の発生時刻はいつか。
Q3.240km地点での主要動の発生時刻はいつか。
\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/
Q1.S波の速さ
S波は主要動を引き起こす原因となる波なので、60km地点と、120km地点での主要動の時間に注目しましょう。
60km地点では11時00分25秒、120km地点では11時00分45秒
つまり、S波は60kmの道のりを20秒で進んだことになります。
これらより、速度は道のり÷時間で求められるので、S波の速さは60(km)÷20(秒)=3(km/秒)となります。
Q2.地震の発生時刻
やり方はQ1の答えを利用する場合と、P波の速さから求める場合の2通りがあります。
まずは、後者で、確かめとして前者を利用して解いていきましょう。
P波は初期微動を引き起こす原因となる波なので、60km地点と、120km地点での初期微動の時間に注目しましょう。
60km地点では11時00分15秒、120km地点では11時00分25秒
つまり、P波は60kmの道のりを10秒で進んだことになります。
これらより、P波の速さは60(km)÷10(秒)=6(km/秒)となります。
このP波が60km進むために要する時間は60(km)÷6(km/秒)=10(秒)です。
発生時刻は0km地点の話なので60km地点の時間から10秒を引いた
11時00分05秒が発生時刻となります。
それでは、前者で合っているか確かめをしていきましょう。
Q1の答えよりS波の速さは3km/秒です。
このS波が60km進むために要する時間は60(km)÷3(km/秒)=20(秒)です。
発生時刻は0km地点の話なので60km地点の時間から20秒を引いた
11時00分05秒が発生時刻となります。大丈夫そうですね。
これにより、P波もS波も発生する時間が同じということが証明されました
Q3.240km地点での主要動の発生時刻
こちらもQ1の答えを利用する場合と、初期微動継続時間に注目するやり方があります。
前問と同じように、まず後者で、その後前者で確かめをしていきましょう。
まず、初期微動継続時間は震源からの距離に比例することを利用します。
60km地点に注目すると、P波が到着してから、S波が到着するまでの時間が初期微動継続時間になるので、
11時00分25秒-11時00分15秒=10秒となるので、60km時点での初期微動継続時間は10秒です。
求めたい240km地点は60km地点の4倍なので、初期微動継続時間も4倍となるはずです。
これらにより、10(秒)×4=40(秒)が240km時点での初期微動継続時間です。
よって、主要動を引き起こすS波が到着する時刻はP波が到着した11時00分45秒の40秒後、11時01分25秒となります。
さて、確かめをしていきましょう。
Q1よりS波の速さは3km/秒なので、120km地点から120km離れた240km地点に着くまでにかかる時間は
120(km)÷3(km/秒)=40(秒)なので、120km地点の11時00分45秒から40秒進んだ、11時01分25秒となります。
いかがでしたでしょうか?
一見難しい地震の速さの問題も、3つのポイントを押さえれば、小学生の算数の力だけで解くことができます。
是非チャレンジしてみてください!!