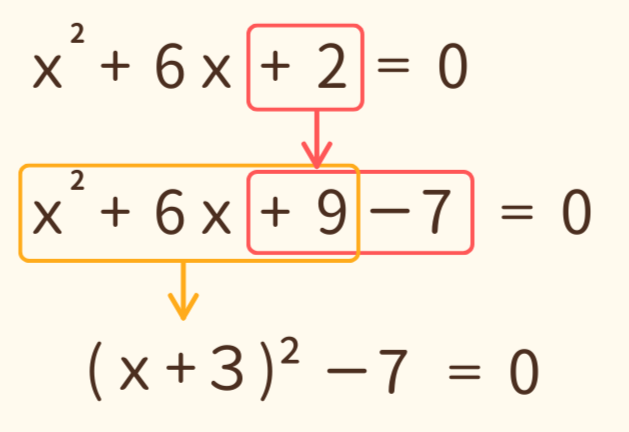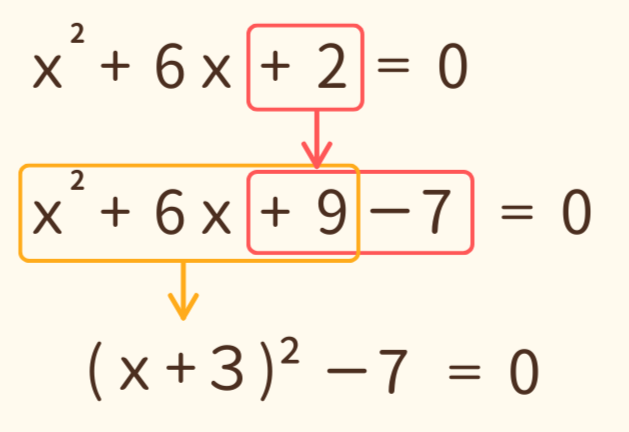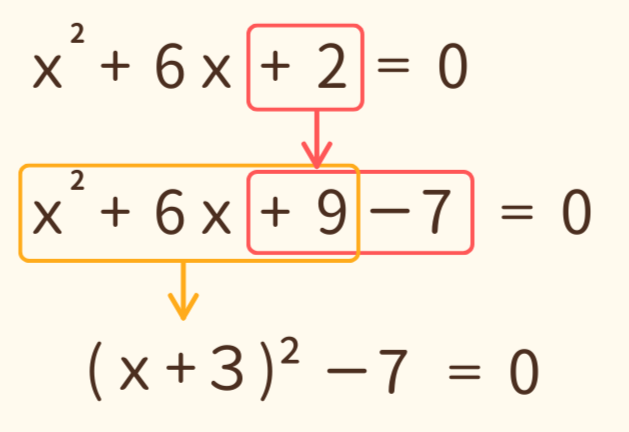今回は、似た熟語や、逆の意味の熟語、一つの単語なのに複数の意味を持つものなどについて解説していきます!
日本語の難しさの1つがこのような言葉の区別にあると思いますが、皆さんならすぐ理解できると思います!では、行ってみましょう。
類義語とは「違う単語だけど似たことを意味する」語のことを言います。文章の中で元の単語をその類義語に変えたとしても、その意味通りに通じることがあります。
例えば、
「彼はいつも青空を眺めながら将来について考えていた。」
という文章の中がある時に、「青空」の部分を類義語の1つである「蒼天」に変えると、
「彼はいつも蒼天を眺めながら将来について考えていた。」
となり、確かに元の文とほぼ同じように意味が通じます。
次に、「将来」を類義語の1つである「まだ見ぬ未来」に変えてみると、
「彼はいつも青空を眺めながらまだ見ぬ未来について考えていた。」
というように、これも元々の文意とほぼ同じになっています。
ただ、類義語は「似ている」言葉なので、必ずしも一致するとは限りません。
では、「考える」の類義語の1つである「決め込む」にすると、
「彼はいつも青空を眺めながら将来について決め込んでいた。」
となり、これは何か自分の中で確定した何かがあるというような文意になり、元々の文とは変わってしまっていますね。
一方で、「思い描く」といった類義語であればうまく当てはまるでしょう。
「決め込む」も「思い描く」も「考える」の類義語ですが、片一方は同じ意味のまま入れ替えられるし、もう片方は別の意味になってしまいます。
このように、言葉には複数の類語があることがほとんどで、その中のいくつかが、元の文と内容をほぼ一致させることが出来ます。(完全に同じではない)
類語は“似た語”でしたが、同義語は“同じ意味の言葉”となります。
例えば、
「本」と「書物」はどちらも紙でできた書き物という意味で完全に一致します。
他にも、「インフルエンザ」と「流行性感冒」は、同じウイルスによる病気ということで同じ意味となります。
類義語と違うのは、入れ替えても完全に文意が一致する点です!
同義語と類義語を一緒にしないように気を付けてください!
対義語は「ある言葉と対の意味を持つ言葉」の事をいいます。
とても簡単に言うとはんたいことばです。
例えば、
「私は寒冷な田舎で生活する。」
という言葉があった時に、寒冷という言葉を対義語である温暖に入れ替えると、
「私は温暖な田舎で生活する。」となります。
寒冷は寒い、温暖は暖かいという意味になるので、この2文は逆の意味になります。
今度は田舎の対義語である都会に入れ替えると、
「私は寒冷な都会で生活する」となります。
田舎と都会は逆の環境なので、文意も逆になっています。
このように、文の一部を入れ替えて逆の意味になる言葉が対義語となります。
他にも、
具体的⇔抽象的
上昇⇔下降
ポジティブ⇔ネガティブ
表⇔裏
鈍感⇔敏感
など、対義語は大体の一般的な単語や言葉にあります。良かったら調べてみて下さい!
多義語とは、一つの言葉が複数の意味を持つ言葉の事です!
たとえば、「甘い」という言葉を考えてみましょう。
例えば、
「このチョコレートは甘い」
というと、このチョコレートは糖分の味がする、という意味になります。
一方で、
「父は娘に甘い」
というと、父は娘に対して厳しさに欠けている、という意味になります。
このように、同じ「甘い」でも、文の内容によって意味が変わってくる言葉を多義語と言います!
\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/
同音異義語とは、同じ音で異なる義(意味)がある語という事です。
「あれ、これって、さっきの甘いと同じでは?」と思うかもしれませんが、それは異なります。そして、ここが今回一番悩ましいところです。
甘いの場合は、甘いという言葉自体に複数の別の意味を持っていて、たまたま同じ音になったわけではありません。
一方で、同音異義語とは違う意味で音がたまたま同じものです。
カンタンな例は「橋(はし)」と「箸(はし)」です。
他には、「石(いし)」「医師(いし)」「意思(いし)」「遺志(いし)」や
「四角(しかく)」「資格(しかく)」「死角(しかく)」「視角(しかく)」
など、全く異なる意味だけど発音(イントネーションを除く)は同じであるものが同音異義語となります。
同訓異字とは、違う字なのに同じ読み方をするものを表す言葉です。
カンタンな例は「熱い」「暑い」です。この2つはどちらも「あつい」と読みます。
これらは偶然同じ読み方になったわけでは無く、どちらも「あつい」という言葉のイメージに準じた漢字を充てられています。したがって、同音異義語ではなく、同訓異字と呼ばれます。
他には、
「測る」「計る」「量る」(“はかる”と読み、ある基準に対する度合いを調べること)
や
「見る」「診る」「観る」「視る」「看る」(“みる”と読み、感覚を働かせて、判断・評価すること)
などがあり、他にも様々な同訓異字があります。