






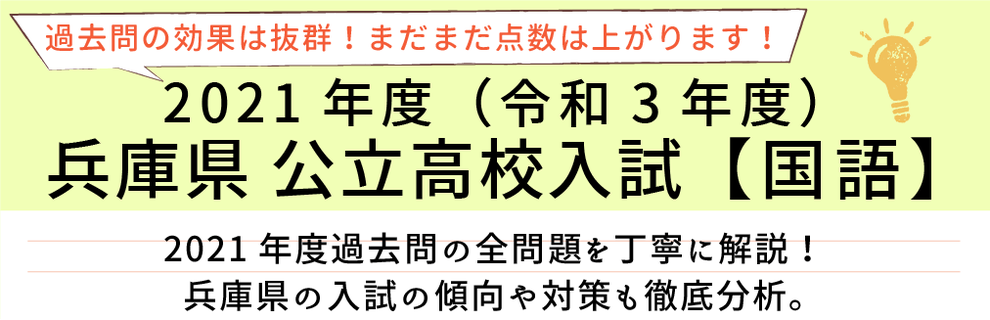
兵庫県の2021年3月実施の令和3年度(2021年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。
受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。
また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。
今年の兵庫県の国語問題は5つの大問から構成され、資料の読み取り問題・漢文・古文・読解問題2つの構成になっています。
難易度としては例年よりもかなり難しく、難だと思います。しかし選択問題が主になるのでハマるといい点数を取れたお子さんもいたかもしれません。大問1は独特な形式なのでしっかりと復習しておくといいと思います。
【兵庫県】令和3年度一般入学者選抜の過去問はこちらから
国語の過去問題はこちら>>
〇〇中学校文化委員会では、芸術鑑賞会のちらしを作成することになった。あとの【ちらし案】は芸術鑑賞会のちらし案、左の【話し合い】はちらし案について文化委員が話し合いをしている場面である。【ちらし案】と【話し合い】を読んで、あとの問いに答えなさい。
問一:【ちらし案】の傍線部①・②の「日和」と同じ意味のことばとして適切なものを、次のア〜カからそれぞれ一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 晴天 イ 日柄 ウ 予定
エ 時期 オ 風向き カ 空模様
問二:【話し合い】の空欄aに入ることばとして適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 発音の強弱 イ 文の区切り
ウ 漢字の読み エ 助詞の使い方
問三:内容紹介文を【話し合い】の全体を受けて書き改めた。書き改めた文章として適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 「今日は降る日和じゃない。」と言う占い師の口車に乗せられて遠出をした男。米屋についたところで大雨が降り出し、米俵をかぶって帰ることになった。ひどい目にあった男は、占い師に仕返しを考える。その仕返しとは!?
イ 遠出をする男に天気を尋ねられた占い師は「今日は降る日和じゃない。」と答えたが、大雨が降り出して男の怒りを買うことになる。講義をする男に占い師は「今日は降る。日和じゃない。」と平然と答えた。男の次なる行動は!?
ウ 遠出の前に、占い師に天気を尋ねた男。占い師の「今日は降る日和じゃない。」という言葉を信じて出かけたが、大雨に振られ米俵をかぶって帰る羽目になった。頭にきた男は占い師に文句を言う。その時の占い師の返答とは!?
エ 男が天気を尋ねたところ、占い師が「今日は降る日和じゃない。」と言うので、男は安心して遠出をしたが大雨になった。次は用心して、あちこちで天気を尋ねて歩く。最後にたどりついた魚屋の返答に男は困惑。魚屋の返答とは!?
問四:【話し合い】の空欄bに入る適切なことばを、【ちらし案】の二重傍線部のことばを使って「⋯「日和違い」!!」に続くように、二十五字以内で書きなさい。ただし、必要に応じて助詞を変えてもよい。
問一:【答え ①カ、②ア】
① 日和には、1天気。空模様。2晴天。晴れたちょうどよい天気。3物事のなりゆき。
の意味がある。占い師の「今日は降る日和じゃない。」という言葉に安心して出かけた男が大雨に降られてしまったことから、占い師の言葉を男は「今日は(雨が)降る天気じゃない。」という意味に勘違いしたと推測できる。よって正解は「天気」と似た意味の、カ(空模様)。
② 占い師の言葉を「雨が降らない天気だ」という意味に勘違いした男の抗議に言い返しているということは、占い師は自分の予報は正しかったと主張したいのだということが推測できる。よって、占い師の言葉の意味は、「今日は降る。晴れじゃない。」という意味で発されたということだ。よって、正解は「晴れ」の意味であるア(晴天)。
問二:【答え イ】
「はるじゃない。」というは、「はる。じゃない。」と「は、るじゃない。」このようにりによってをえることがる。よって、はイ。
問三:【答え ウ】
内容紹介文について、話し合いで決まった内容をまとめると以下のようになる。
①「今日は降る日和じゃない。」というせりふはそのままにする。
②すべて説明する必要はない
→・続きが気になるようにするため、いとのやりとりの種明かしになる部分は書かない。
・男が魚屋に天気を尋ねる場面は書かない。
②より、イ、エは選択肢から外れる。また、アの”男の占い師に対する仕返し”に関しては提示されている物語の内容の中で特に言及がない。よって、ウが適当。
問四:【答え 兵五師匠が本校生のためにわかりやすくアレンジした(「日和違い」!!)】
話し合いによってをわないことが決まったため、「ちらし」の「兵五師匠が本校生のためにわかりやすくアレンジしてくださった」の部分を後半にうまくつながるように敬語を使わず表現すればよい。よって、解答例のようになる。
次の文章は、古代中国の魯の国の君主が、粗末な身なりで耕作していた曽子を見かねて、領地を与えようと使者を遣わしたときの話である。次の書き下し文と漢文を読んで、あとの問いに答えなさい。
問一:傍線部①が表す意味と同じ意味の「修」を含む熟語として適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 修行 イ 修得 ウ 監修 エ 改修
問二:書き下し文の読み方になるように、傍線部②に返り点をつけなさい。
問三:二重傍線部a・bが指す人物として適切なものを、次のア〜エからそれぞれ一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 魯の君主 イ 曽子 ウ 使者 エ 筆者
問四:本文の内容として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 領地を受け取ってしまえば、魯の君主に対して卑屈にならずにはいられないと思ったので、曽子は受け取らなかった。
イ 求めてもいない領地を与えようとする魯の君主の行為には、何かしら裏があると感じたので、曽子は受け取らなかった。
ウ 自分のような者が魯の君主から領地を受け取るのは、あまりにおそれ多いと思ったので、曽子は受け取らなかった。
エ 安易に領地を与えようとする振る舞いにおごりの色が見え、魯の君主に不信感を抱いたので、曽子は受け取らなかった。
問一:【答え エ】
曽子の粗末な身なりを見かねた魯の君主が、曽子に領地を与えようと遣わした使者の発言であることから、「領地からの収入で衣服を修繕しなさい。」という意味の発言をしたと読み取れる。よって、「修繕」と似たような意味の後の中で「修」が用いられているエ(改修)が正解。
問二:【答え 】
きしのにびえると、「」となる。よって、のにレ、のにレが。レとのいをしておこう。
問三:【答え a イ b ア】
a 「臣」には家来、臣下という意味のほかに、自分自身をへりくだって言う場合にも用いられる。
2重傍線部aを含む発言は、「どうして領地を受け取らないのか」という使者の質問に対する、曽子の理由の回答である。よって、曽子の発言は「私は~と聞いたから(受け取らないのだ)。」という意味であると推測できる。
よって、答えはイ。
b 2重傍線部bを含む発言を現代語に直して意訳すると、「わたくしめは、人に何かを貰った者はその人に対して畏れ多く、かしこまるようになり、人に何かを与えたものは与えた人に対して(地位や権力に対して)誇り、思いあがるようになると聞きました。たとえ”子”が私に領地を下さって私に対してそのようにおごり高ぶらないことがあったとしても、私は”子”のことを畏れ多く思い、かしこまるようにならずにはいられないでしょう。」という意味になる。ここで、曽子に対して領地を与えようとしているのが、魯の君主であるということを考えると、子=魯の君主となり、正解はア(魯の君主)である。
問四:【答え ア】
ア~エの選択肢はすべて、曽子がなぜ領地を受け取らなかったのか、その理由を説明している。曽子が領地を受け取らなかった理由は曽子の最後の発言から読み取ることができる(問3bの)。また、「我能く~勿からんや。」が反語文であり、「畏れないでいられるだろうか、いや、いられない」という意味になっている。よって、領地を受け取ってしまうと君主に対してへりくだらずにはいられないというになっているアが正解。
ウ 「あまりに畏れ多いと思ったので」受け取らなかったわけではない。
イ 曽子が君主の行為に裏があると感じた場面は本文中に無い。
エ 曽子が君主の態度におごりを感じ、不信感をい場面は本文中に無い。
次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。
問一:二重傍線部を現代仮名遣いに改めて、全て平仮名で書きなさい。
問二:傍線部①の意味として適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア でたらめな イ したたかな
ウ おおざっぱな エ ぜいたくな
問三:傍線部②の本文中の意味として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア はなやかな イ 縁起がよい
ウ すばらしい エ 珍しい
問四:傍線部③について、所持した順番として適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 潭北→源吾→筆者 イ 筆者→源吾→潭北
ウ 源吾→潭北→筆者 エ 源吾→筆者→潭北
問五:傍線部④の理由として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 品質を裏付ける証拠もないのに後生大事に茶碗を持っているのは恥ずかしいことだから。
イ 高価な茶碗だからといって所持することにこだわるのは風流の道に反することだから。
ウ 人からもらった茶碗をいつまでも自分の手元にとどめておくのは欲深いことだから。
エ いずれ不確かになるような来歴をありがたがって茶碗を所有するのはむなしいことだから。
問一:【答え いにしえ】
歴史的かなづかいを現代的かなづかいに直すとき、以下のようになる。
①語頭以外の「は・ひ・ふ・へ・ほ」→「わ・い・う・え・お」
②母音が「au」「iu」「eu」→「o」「yu」「yo」
③「む」→「ん」
④「ゐ」「ゑ」「を」→「い」「え」「お」
⑤「くわ」「ぐわ」→「か」「が」
⑥「ぢ」「づ」→「じ」「ず」
問二:【答え ア】
「のもないのにかくしをのものとしてでている」というからえると、アの「でたらめな」がもしていることがかる。
問三:【答え ウ】
の「めでたし」は、
①すばらしい。だ。だ。
②ばしい。うべきだ。
というがある。よってえはウ。
問四:【答え ウ】
傍線部③を含む1文から整理すると、潭北が所持した高麗の茶碗は、源吾が秘蔵した物だった。よって、源吾→潭北の順。そして、今は余(私)のところに譲り受けてあるということがわかる。よって持ち主の流れは、源吾→潭北→私(筆者)で正解はウ。
問五:【答え エ】
傍線部④は「他人にあげてしまった」と言っている。その前を見ると、「のちのちはかの咸陽の釘かくしの類ひなれば、」と書いているので、筆者は「咸陽の釘かくし」のような状況になることを嫌がって、茶碗をにあげたということがわかる。前半の「釘かくし」の話は、「ある人が、釘かくしを咸陽宮からの由緒あるものとして大切にしていた。しかしその来歴は本当かどうかわからないため、そのようなことを言っているのはむなしい。」という筋であった。よって、前半の「釘かくし」の話しでの筆者の考えに最も近いエが正解。
ア 「品質を裏付ける~」が間違っている。その物が持つ歴史が正しいと証明できないことが問題。
イ 高価な物であるかどうかは議論に上っていない。風流さに関する記述も本文中にない。
ウ 「人からもらった」ということは問題ではない。欲深さに関する記述も文章中にない。
次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。
問一:傍線部①・③・⑤の漢字の読み方を平仮名で書きなさい。
問二:傍線部②・⑧の本文中の意味としてなものを、ののア~エからそれぞれ一つ選んで、その符号を書きなさい。
② ア ふるえて イ あからんで ウ ひきつって エ ゆるんで
⑧ ア 身動きがとれなく イ 考えをまとめられなく ウ 不安に耐えられなく エ 落ち着いていられなく
問三:点線部で使われている表現技法として適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 対句 イ 擬人法 ウ 省略 エ 倒置
問四:傍線部④の表現の説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 無機物である石の気持ちさせ理解することができるくるみの感受性の豊かさを表している。
イ 他人の言うことに耳を貸さず趣味について語り続けたくるみのひたむきさを表している。
ウ 相手に左右されることなく自分の判断で行動するくるみの内に秘めた強さを表している。
エ かみ合わない会話で気まずくなった雰囲気を意に介さないくるみの大らかさを表している。
問五:傍線部⑥の清澄の様子の説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 誤解を招いてしまったことに戸惑い、何とか取り繕おうとした清澄に宮多の素朴な返信が届いた。清澄は読めば読むほどkまりの悪さを感じるとともに、誠実でなかった自分の態度を後悔している。
イ 勇気を足して本心を伝え得たことに満足していた清澄のもとに届いた宮多の返信は、賞賛の言葉に満ちていた。その言葉を読むごとに、清澄は自分の決断は正しかったとの思いを強くしている。
ウ 孤立さえ受け入れようと考えていた清澄に届いた宮多の返信は、意外なものだった。その飾らない言葉を読むにつけ、清澄は思い込みにこり固まっていた自分の心がほぐれていくのを感じている。
エ 謝罪が受け入れられるかどうか不安に包まれてたが、宮多からの返信は清澄への思いやりにあふれていた。清澄は、読むほどに人の優しさが身にしみ、人との接し方を見直そうとしている。
問六:⑦からうかがえる清澄の刺繍に対する考え方の説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 時とともに移ろい形をとどめるはずのない美しさを、布の上で表現することこそが理想の刺繍である。
イ 布の上に美しく再現された生命の躍動によって、見る人に生きる希望を与えるものこそが、目指す刺繍である。
ウ 揺らめく水面の最も美しい瞬間を切り取って、形あるものとして固定することこそが、求める刺繍である。
エ ただ美しいだけでなく、身につける人に不可能に挑む勇気を与えるものこそが、価値のある刺繍である。
問七:傍線部⑨の清澄の様子の説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 周りの人たちに理解してもらえず、焦って空回りしていた自分を冷静に振り返ることができた今、周囲の目を気にせず、純粋にドレスづくりに打ち込むべきだと自分を奮い立たせている。
イ 率直に周囲の人たちと向き合えば、互いの価値観を認め合う関係を築くことができると気づいた今、自分を偽ることなく新たな気持ちでドレスづくりに取り組んいこうと決意を固めている。
ウ わからないものから目を背けてきた自分の行いを反省し、未知のものを知ろうとすることによって新しい着想が得られた今、次こそは姉を喜ばせることができるという期待に胸を躍らせている。
エ 友人に心を開き、受け入れられた経験を通して、刺繍という趣味への自信を取り戻した今、クラスメイトと積極的に交流し、楽しみを共有できる関係を築くことから始めようと決心している。
問一:【答え ①みちばた ②そんちょう ⑤ほ(められた)】
問二:【答え ②イ ⑧エ】
問三:【答え エ】
ア 誤り。対句は、よく似たものや反対のものを使い、同じ構成でセットになっているような文のこと。例えば、「雲は白い、海は青い」のようなものがある。
イ 誤り。擬人法は、でないものを人間のように表現すること。例えば、「風のささやき」「太陽が歌う」のようなものがある。
ウ 誤り。省略は、文章を簡単にするために一部をはぶくこと。
エ 正しい。「僕は○○ということに気づいてしまった。」というのが入れ替わって「僕は気づいてしまった。○○ということに。」となっている。このようにを逆にすることを倒置法という。
問四:【答え ウ】
傍線部④とその前の清澄とくるみのやり取りをもとに選択肢を判断していく。
直前の2人のやり取りから、くるみの”趣味に関して、他人の視線や評価を気にしない態度”がわかる。それを踏まえて考えると、「ずんずんと前進していくくるみの後ろ姿」からは”くるみの趣味に対してまっすぐで強い性格”を読み取ることができる。よって、このどちらの要素もきちんと含んだウが正解。
イと悩むかもしれないが、「他人の言うことに耳を貸さず、語り続けた」という点がズレている。くるみは真澄の言うことをきちんと聞いて、会話をしている。話を聞いていないのではなく、他人の評価を気にしていないというところが大切。
ア のちをできるというはない。
エ はくるみとのを「おもしろかった」とっているためり。
問五:【答え ウ】
メールを送る前の真澄と、返信が着た後の真澄に分けて考えてみる。
〈メールをるの真澄〉
「刺繍の趣味を打ち明けるときっと一人になる。それは寂しいけど、好きなことに嘘をつくのはもっと寂しい」→「一人になるかもしれないけれど、その覚悟の上で趣味を打ち明けよう」というのきをみれる。
〈宮多からの返信を見た真澄〉
「宮多の返信が自分の趣味を否定するものでもなく、単純に誉め言葉だったことに対する驚き」→「今まで自分の趣味を理解してもらえなかったから、決めつけていた、諦めていたという気づき」→「涙がにじむほど、緊張していた心がやわらぐ」というのきをみれる。靴紐以降の表現は、情景描写だが、真澄の心を投影した表現である。
よって、前半のきなをきだとうことでするとえていたこと、後半の驚きとほっとした気持ちが両方表現されているウが正解。
問六:【答え ア】
傍線部⑦の「あれ」が何なのか具体的に言い表すことができれば真澄が刺繍で表現したいものがわかる。⑦を含む段落をまとめると、”きらめくものや揺らめくものは触れられないし保管もできないから、美しい。しかし刺繍で表現すれば触ることができる”という真澄の気持ちが読み取れる。よって、真澄が表現したい「あれ」とは、きらめくものや揺らめくもののような、儚いものであるとわかる。よって、それをなく言い表したアが正解。
ウはがしたいのひとつではあるかもしれないが、がされすぎてしまうためとはえない。
問七:【答え イ】
友人関係とドレスのことを分けて考えると、友人関係では、素直に自分のことを打ち明けた宮多とのメールのやりとりを通して、自分の趣味はばかにされるという思い込みが解け、自分も相手の好きなことを知るために素直に向き合おうとしている。
ドレス作りに関しては、今回の経験から、姉に向けてどんなメッセージ性を持ったドレスを作るかイメージが固まってきている。えがどんどんがって、いてもたってもいられなくなり、をびしていでにろうとしていることがみれる。
よって、友人関係とドレスづくりのどちらのことも過不足なく表現されたうえで、くってドレスづくりにりもうとするがされているイがである。
ア 誤り。周囲の目を気にしないのではなく、お互いに歩み寄り、認め合う努力をしようとしている。
ウ 誤り。未知のものを知ろうとすることで新しい着想を得たこと、姉を一度喜ばせることができなかったことが文章中から読み取れない。
エ 誤り。ドレスづくりにちたにりもうとするがされていない。
次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。
問一:二重傍線部A〜Cの漢字と同じ漢字を含むものを、次の各群のア〜エからそれぞれ一つ選んで、その符号を書きなさい。
A ア 失敗をケイ 機に改善する。 イ ケイ 勢が悪化する。
ウ 小説にケイ 倒する。 エ 審議をケイ 続する。
B ア 破テン 荒の大事業。 イ 針路を西へテン 回する。
ウ 和様建築のテン 型。 エ 領収書をテン 付する。
C ア 装飾にイ 匠を凝らす。 イ イ 大な芸術家。
ウ どの意見も大同小イ だ。 エ イ 厳に満ちた声。
問二:文中の点線部について、文脈を踏まえると「自力で」という文節はどの文節に係るか。文節で抜き出して書きなさい。
問三:傍線部①の本文中の意味として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 作者への評価が正当かどうか。 イ 作者を特定しやすいかどうか。
ウ 作者の責任が重いかどうか。 エ 作者が実在するかどうか。
問四:傍線部②の説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア チェックする人数にかかわらず、内容への信頼は保たれる。
イ チェックする人の能力に関係なく、内容への信頼は保たれる。
ウ チェックする人の能力が高いほど、内容への信頼が高まる。
エ チェックする人数が多いほど、内容への信頼が高まる。
問五:③について、筆者が考える「情報」と「知識」の関係を説明した次の文の空欄a・bに入る適切なことばを、aはあとのア~エから一つ選んで、その符号を書き、bは本文中から十字で抜き出して書きなさい。
【 a 】ことによって、手に入れた情報と既存の知識や情報とが【 b 】ように結びついたとき、情報は知識の一部となる。
ア 複数の情報を一つのまとまりとして理解しようとする
イ 情報技術を駆使して多くの情報を集めようとする
ウ 集めた情報について一つ一つの構造を読み解こうとする
エ 多くの情報から有益な情報だけを取得しようとする
問六:傍線部④とはどういうことか。その説明として最も適切なものを、次のア〜工から一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア コンピューターが大量の情報を体系的に整理してしまうため、自分の力で情報を集めて整理する方法が取得できなくなること。
イ 知識に基づく探索なしに目的の情報が得られるため、探索の過程で認識するはずの他の情報との関係に気付かなくなること。
ウ 容易に情報が入手できる環境に過度に慣らされることによって、ネット検索やAIを用いた情報の探索さえしなくなること。
エ 目的の情報を探し当てようとする意識がなくても目的が達成されることで、知識を身につける意義が感じられなくなること。
問七:傍線部⑤の説明として最も適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 本に書かれた著者の意見をうのみにするのではなく、本の中の情報をもとにして自分なりの考えを形成しながら読み進めること。
イ 本の著者が取り上げた情報と取り上げなかった情報とを比較することにより、情報の選び方に現れた著者の個性を感じ取ること。
ウ 本から得た情報を自己流でつなぎ合わせようとするのではなく、本の記述に基づいて、まず著者の思考の過程を追体験すること。
エ 本の記述について、隠れた意味を読み取ろうとするのではなく、著者が作り上げた個性的な論理的展開に従って素直に読むこと。
問八:本文に述べられている内容の説明として適切なものを、次のア〜エから一つ選んで、その符号を書きなさい。
ア 知識は、幹に相当する情報と、枝や葉に相当する情報が組み合わさった構造から樹木にたとえることができ、新しい理論のおうな価値のある情報は、その有効性から実にたとえることができる。
イ 本を読めば、私たちは豊富な知識を得ることができるが、獲得した知識を発展させていく場合には、本に書いてる情報を自分で考えた論理でつなぎ合わせてしまわないよう注意が必要である。
ウ 単に知識を得るだけなら、本を読むよりもネット検索を活用することによって効率的に研究を進めることができる。
エ 理論面での整合性が保たれる限り、情報と情報との結びつけ方に制約はないので、私たちは身につけた知識を別の情報や知識と結びつけていくことによって、知識をさらに広げることができる。
問一:【答え A ウ B イ C エ】
A 傾向
ア 契機 イ 形勢 ウ 傾倒 エ 継続
よって、正解はウ。
B 転化
ア 破天荒 イ 転回 ウ 典型 エ 添付
よって、正解はイ。
C 権威
ア 意匠 イ 偉大 ウ 大同小異 エ 威厳
よって、正解はエ。
問二:【答え 知る】
「自力で」がかかっている可能性のある動詞は、「歩く」「知る」がある。(自力で―失う、自力で―あるは意味が繋がらない。)の「森」という抽象的な表現をそののをにになる言葉になおすと、は”自力で自分がどんな情報を求めているのか知る能力を失っていく可能性がある”となる。ここから、「自分がどんな情報を求めているか(どんな森を歩いているのか)」がひとつのかたまりであることがわかる。よって、正解は「知る」。
問三:【答え イ】
「作者性」については1,2段落に書いてある。内容に関する責任の所在は、本のは「著者」というので、ネットのは「みんな」である。ネットのは、なのによってりげられるため、のはしい。よって、エが正解。作者の存在について言及しているイと迷うかもしれないが、ネットのもではあるがのがきんだものであるためり。
問四:【答え エ】
「相対的」とは、「他のものと比較して物事を成り立たせること」である。つまり、②を含む全文をわかりやすく解釈すると、”複数人のチェックによって、それら複数の判断の比較の中でが出来上がっていくため、すべての人の「正しい」の平均に近づいていくという観点から、「正しい」。”という意味になる。この、”すべての人の平均に近づく”ことを限りなく実現させるには、エの”チェックする人数の多さ”が必要になる。よって、エが正解。
「相対的」という表現はよく用いられるので、基本的な意味を押さえておこう。
問五:【答え a ア b としてをなす】
”手に入れた情報と既存の知識や情報とを結びつける”ことについて言及されている3段落目の最後の文を参照すると、
”その情報が、既存の情報や知識と結びついてある状況を解釈するための体系的な仕組みとなったとき~知識の一部となる”とある。
ここから、情報が知識の一部になるには、新しい情報と既存の情報や知識が”体系的な仕組み”になるように結び付けられる必要があることがわかる。これとでにったをすと、5の「としてをなす」がbにてはまることがかる。
以上より、aには”体系的な仕組みになるようにするためにはどのような姿勢や取り組みが必要か”を表現する言葉が入ることがわかる。「体系的」とは”一つ一つのものがある秩序や論理にしたがってまとまっている様子”を指す。つまり、情報を知識の一つにするには、”得られた情報と既存の情報や知識を秩序に沿った一つのまとまりにする”ことが必要である。よって、aには”のをひとつにまとめようとする”ことに言及されているアが入る。
問六:【答え イ】
ア 誤り。コンピュータは知識を断片化して、大量の情報として扱っているため、そこに体系的に整理されているとは言えない。(11段落最終文参照)
イ 正しい。11段落の本での情報収集に関する記述、7段落のAIによる情報収集の特徴から、正しい選択肢であることがわかる。
ウ 誤り。7段落目に、検索する前に情報を得られるかもしれないという内容の記述はあるが、そもそもネット検索やAIを用いた情報収集をしなくなるとは述べられていない。
エ 誤り。”知識を身につける意義”の感じ方の変化に関する記述は無い。
本文の広い範囲を選択肢の正誤判断に必要とする問題は、選択肢を一つずつ読み、選択肢に関係する記述があったところを必要に応じて振り返りながら、消去法で考えるとわかりやすい
問七:【答え ウ】
傍線部⑤を含む段落から、よい読書と悪い読書の特徴をまとめると、
よい読書
・論理的展開を読み込んでいける
悪い読書
・表面上の記述に囚われる
・本の表面の部分部分を自分勝手な論理でつないでしまう
となる。つまり、よい読書とは、自分勝手な論理で表面的に読み進めるのではなく、著者の論理的展開を読み込もうという姿勢をもって取り組むものであることがわかる。よって、正解はこれらの要素を含んだウ。
選択肢ア、イなどは一般的に間違ったことは言っていないように思えるため、選択してしまいそうになるかもしれないが、あくまで本文に似たような記述があるかを基準として考えるようにしよう。
問八:【答え エ】
ア 誤り。木を用いた比喩は5段落以降に記述がある。そこから、葉や実や枝=情報、幹=社会的に蓄積されてきた知識の構造をつくる大枠になる部分であることがわかる。つまり、”幹に相当する情報”という部分は誤っている。
イ 誤り。本の読み方は9段落に記述がある。”本に書いてある情報を自分で考えた論理でつなぎ合わせてしまわないこと”は、「よい読書」をするときに必要なことであって、知識を発展させていく場合に必要な姿勢とは書かれていない。
ウ 誤り。11段落から、ネット検索では情報を得ることはできるが知識を得ることはできないことがわかる。
エ 正しい。
正解はエだが、直接的に根拠としてわかりやすく指せる部分がないため、すぐに答えにたどり着くのは難しいだろう。消去法で、本文と見比べた正誤判断がわかりやすくできる選択肢から消していくのがよい。
家庭教師のやる気アシストは、兵庫県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。
おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。
高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!
家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!
お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?
お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。
たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?
やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。

