






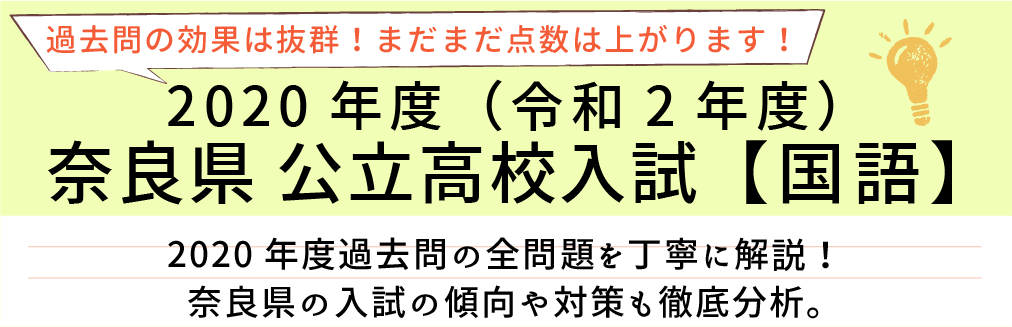
奈良県の2020年3月実施の令和2年度(2020年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。
受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。
また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。
奈良県の国語は読解問題2つ、古文1つ、作文問題1つの計4つの大問から構成されます。大問の順番は年度毎に異なりますが、構成自体は変わりません。
難易度としてはやや難です。記述の割合が少し多いですが、問題自体はオーソドックスな問題が多いです。最近では「行書」が出てくるのも特徴の一つに上げられるかもしれません。
【奈良県】令和2年度一般入学者選抜の過去問はこちらから
国語の過去問題はこちら>>
問1:A,Dの漢字の読みをひらがなで書き、B,Cの片仮名を漢字で書く問題です。
【・答え「A:はな B:転 C:防 D:こうけん」】
問2:傍線部①の文脈上の意味として適切なものをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「ウ」】
代名詞とは、「そのものを典型的に表しているもの」という意味で、傍線①の場合は、西芳寺はコケの庭園が有名で「苔寺」と呼ばれている。つまり、西芳寺を代表するものが、「コケ」となる。よってウが適切。
問3:傍線部②を説明したものとして適切なものをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「イ」】
傍線②より前の段落において、「日本庭園ではもともとコケは使われておらず、室町時代の応仁の乱の後に寺が荒廃し、いつしか庭園が広くコケに覆われるようになった。」とあるので、イが適切。
問4:傍線部③とあるが、そのように言えるコケの印象を表している言葉を、文章中から抜き出す問題です。
【・答え「静かで質素なものがもつ美しさ」】
傍線③の理由が③より後の段落で説明されており、コケの印象を「静かで〜コケの印象」の部分が当てはまる。
問5:傍線部④とあるが、コケの緑が季節の移ろいをひきたてるとは、具体的にどういうことか。「コケの緑が、」に続け、これを含めて30字以内で記述する問題です。
【・答え「例:コケの緑が、桜や、夏椿、紅葉、真っ白な雪を際立たせること。」】
傍線④について、直前の文章「春には桜が〜雪が覆う」の部分が説明になっているので、そこをまとめるとよい。
問6:「日本十進分類法」に従って分類されている図書館でコケの生態を調べるためにどの分類の本棚を探せばよいのかア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「イ」】
コケの生態についてなので、生物に関わる自然科学に分類される。
問7:文章中の和歌について述べた文章の中のXに当てはまる3字以内の言葉と、Yに当てはまる言葉を文章中から抜き出す問題です。
【・答え「X:たとえ Y:めでる感性」】
ここでは、コケが生えている様子を「敷物」に例えているので、Xには、「たとえ」が入る。Yには、和歌を詠んだ人に美意識を感じるものが備わってるということなので、和歌の直前の文にある、「めでる感性」が入る。
問1:傍線部①に関して、「伺う」の敬語の種類をア~ウの中から選ぶ問題です。
【・答え「イ」】
「伺う」は「聞く」の謙譲語です。
問2:傍線部②に関して、人々は周囲の状況をどのようにして認識してきたか述べられている部分を抜き出し、初めの5字を書く問題です。
【・答え「音を聞いて」】
傍線②のような家の作りによって、鳥の鳴き声、風や雨の音、生活の音など、つまり、文章中の、「音を聞いて想像力を働かせ情報を得てきました。」の部分が当てはまる。
問3:傍線部③の文とその直前の文をつなぐ接続詞として適切なものをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「ウ」】
直前の文章を傍線③で言い換えているので、「=イコール」の関係になる。よって、接続詞としては、ウの「つまり」が適切。
問4:文章中のⅠの部分では、父が語った「オノマトペ」にまつわる話が述べられている。「書く人」としての筆者が、仕事がうまくいかず、父が語った「オノマトペ」を無意識に口にするとき、この言葉は筆者にとってどのような言葉か文章中の言葉を用いて45字以内で記述する問題です。
【・答え「例:幼いときのワクワクした気持ちがよみがえり、原稿を書き進めることができる、おまじないの言葉。」】
[ I ]の中の、「仕事がうまく〜言葉なのです。」の部分で筆者にとって父が語った「オトマトペ」がどのような言葉なのかが説明されているので、そこを要約する。
問5:傍線部④に関して、少年の言葉を聞いて筆者はどのように考えるようになったかをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「ア」】
傍線④よりあとの、「言葉って〜相手に伝わる」とあるので、アが適切。
イ:「弾むような言葉遣いは父にしかできないと考えていた」とは書いてないので不適切。
ウ:考える順序が逆なので不適切。本文では、言葉の意味が重要だと考えていたが、心地よいリズムさえあれば相手に伝わるものだと考えるようになったとある。
エ:「言葉の意味は必要ないと考えるようになった」という記述はないので不適切。
問6:この文章の表現上の工夫とその効果について述べたものとして当てはまらないものをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「エ」】
ア:本文中において、読者に問いかけているので適切。
イ:ブラジルの少年とのやりとりなど具体的に述べられているので適切。
ウ:日本の家屋に例えるなど、場面をイメージしやすくしているので適切。
次の□内は、陽一さんが書いた、クラスの目標の【下書き】と【清書】をみて、改善点として適切なものをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「エ」】
[下書き]では、「や」や、「り」などが中心からずれているが、[清書」では、きちんと中心を捉えている。また、「下書き」では、平仮名が大きくバランスが悪いが、[清書」では、小さめに書いてあり、全体のバランスがよい。
問1:傍線部①の「いささかも」が直接かかる部分をア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「ア」】
「いささかも」は副詞で、「少しも〜ない」つまり打ち消しの語にかかる。
問2:傍線部②の意味として適切なものをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「ウ」】
「このめし〜ことなけれども」食事をする事は、1日3回欠けることはないけれども」となるので、ウが適切。
問3:この文章で筆者は、食事の例を取り上げて、何かを身につけるためには何が大切であると述べているか適切なものをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「エ」】
物事を行うのに、「かくせんと思ふこころざし」が大切だと言っているのでエが適切。
問1:傍線部が「時間がかかる」という内容を表すとき、( )にどのような言葉が入るか適切なものをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「エ」】
「時間がかかる」という内容にしたいが、傍線部では、( )にできるものではない。と打ち消しになっているので、「時間がかかる」とは逆の意味の言葉が入る。よって、エの一朝一夕(きわめてわずかな時間)が適切。
ア:一進一退は「状況や事態が進んだり、後退したりすること」
イ:一長一短は「人や物事には、良い面も悪い面もあるということ」
ウ:一喜一憂は「状況の変化などちょっとしたことで、喜んだり不安になったりすること。また、まわりの状況にふりまわされること」
問2:春香さんはどのような意図で質問したと考えられるか適切なものをア~エの中から選ぶ問題です。
【・答え「ウ」】
山田さんに、奈良の木を使っている理由をたずね、さらに奈良の木の特徴を聞き出そうとしているのでウが適切。
ア:具体的な例を聞き出そうととはしていないので不適切。
イ:発言の意図を確かめるような内容はないので不適切。
エ:他の考えは聞いていないので不適切。
問3:地域に方にインタビューをすることになったとき、どのようなことに気を付けるかあなたの考えを記述する問題です。
【・答え「例:私は、「なぜ」や「どうして」などの疑問詞を使うようにしてインタビューします。疑問詞を使うことで、相手の方が答えやすくなるからです。また、返答も具体的にしてもらえるので、より詳しい情報が得られるからです。」】
※生徒たちのインタビューでは、必ず疑問文になっているので、山田さんが答えやすい構造になっている点、そしてより詳しく情報を聞き出している点に着目し、どのようにインタビューすれば良いかを考えて答えるとよい。
家庭教師のやる気アシストは、奈良県にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。
おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。
高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!
家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!
お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?
お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。
たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?
やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。

