






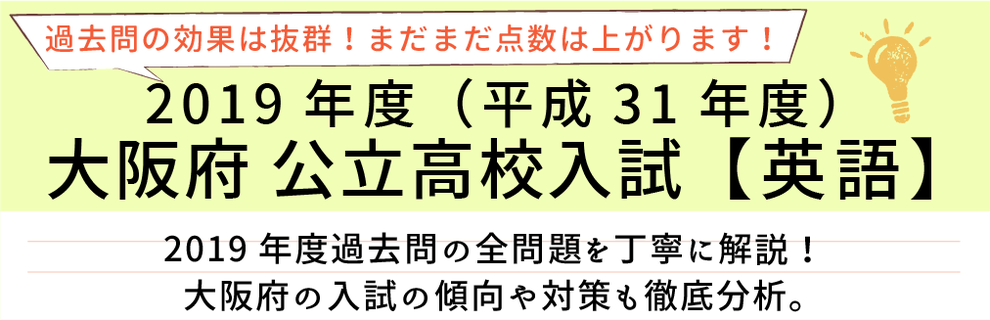
大阪府の2019年3月実施の平成31年度(2019年度)入学者の公立高校入試問題の解説をしています。
受験勉強において、過去問を解くことはとても効果的な勉強法です。ぜひ、受験までに一度挑戦し、問題の傾向を掴んでおきましょう。合わせて、対策などをたてられるととても良いですね。
また、過去問で苦手な点が見つかった場合は、そこを中心に試験日当日までにしっかりと対策しておきましょう。
大阪府の英語の問題は、難易度としては全体的に高く、Aがやや易、Bが難、Cが激難といったところです。
Cに至っては大学入試に近いような印象さえ受けます。設問もオールイングリッシュで書かれています。
【大阪府】平成31年度一般入学者選抜の過去問はこちらから
英語Aの過去問題はこちら>>
英語Bの過去問題はこちら>>
英語Cの過去問題はこちら>>
英語リスニングA・B問題はこちら>>
英語リスニングA・B音声はこちら>>
英語リスニングC問題はこちら>>
英語リスニングC音声はこちら>>
問1:文中の()に日本語の文の内容と合致する名詞を選ぶ問題です。
【・答え イ】
イのlibrary を選ぶ。oftenは頻度を表す副詞。go to theの目的語を選ぶ問題で、「その図書館に行きます」とあるため、イを選ぶ。
問2:文中の()に日本語の文の内容と合致する形容詞を選ぶ問題です。
【・答え ア】
アのcloudy を選ぶ。天気を表すときは無生物主語itをよく主語に使う。「くもっていました」とあるため、アを選ぶ
問3:文中の()に日本語の文の内容と合致する形容詞を選ぶ問題です。
【・答え ウ】
ウのpopular 人気の を選ぶ。ここでの語順には注目されたい。冠詞+副詞+形容詞+名詞 となるため、この問題では、a (冠詞)+very(副詞)+popular(形容詞)+story (名詞)となる。
問4:文中の()に日本語の文の内容と合致する動詞を選ぶ問題です。
【・答え ウ】
ウのwrite 書くを選ぶ。Please +動詞の原型の命令文の形。命令文は動詞の原型を文頭にもってくる。on the card の onには、壁や紙にぴったりひっつくイメージを持ってほしい。今回だと、カードに名前がぴったりひっつくイメージ。
問5:文中の()に日本語の文の内容と合致する前置詞を選ぶ問題です。
【・答え ア】
アのbetween 〜の間に を選ぶ。between A and B 、A とB の間に のように使われる。(3)でのamongの〜の間に と混合しないように注意してほしい。
問6:文中の()に日本語の文の内容と合致するbe動詞を選ぶ問題です。
【・答え ウ】
be動詞の原型be、単数に用いられるis、複数に用いられるareを確認。今回はrestaurants が複数なのでウのare を選ぶ。
There +be動詞〜 で 〜がある の意味。
問7:文中の()に文法的に正しい単語の形を選ぶ問題です。
【・答え イ】
動詞の正しい形を選ぶ問題。過去形のイ listened を選ぶ。ウのlistening は、現在進行形としてbe動詞+動詞+ingの形で使われることが多い。
I’m listening to my favorite song.のように。
問8:文中の()に文法的に正しい単語の形を選ぶ問題です。
【・答え イ】
イのnewerを選ぶ。アのnewが基本の形。イのnewerが比較級。ウのnewestが最上級。
「〜よりも」の場合は、比較級+than〜の形を用いる。This computer is newer than that computer.のように。
問9:文中の()に文法的に正しい単語の形を選ぶ問題です。
【・答え ア】
アのdoを選ぶ。助動詞のあとにくる動詞は原型を用いる。must+動詞の原型で 〜しなれけばならない という意味になる。
問10:文中の()に文法的に正しい単語の形を選ぶ問題です。
【・答え ウ】
現在分詞のウのplayingを選ぶ。分詞が修飾する単語(今回だとthat boy)が能動的(その行為をする側)なのか受動的(その行為をされる側)なのかを考えると解きやすい。that boy(その少年)がピアノを弾く(能動的)のか、弾かれる(受動的)のかを考える。すると、「その少年が弾かれる」のではなく、「その少年がピアノを弾く」ほうが自然と考えられる。その場合は、能動的な現在分詞(playing)を選ぶ。
問1:選択肢のうち、本文中の空欄①に最も適している前置詞を選ぶ問題です。
【・答え ウ】
前置詞選択問題。ウの期間を表す前置詞forを選ぶ。for three weeksで、3週間を表す。
問2:選択肢のうち、本文中の空欄②に最も適している関係詞を選ぶ問題です。
【・答え ア】
疑問詞選択問題。アのhowを選ぶ。2段落目の3行目にby bike and train とあるから、どうやってその湖に行くかの手段を尋ねたと推測できる。そのため、②にhowを挿入し、「how to go there 」「どうやってそこに行くか」という文章にする。
問3:下線Ⓐを表している内容を本文中から英語4語で抜き出して答える問題です。
【・答え a space for bikes 】
itが示す内容を抜き出す問題。itを含む文の意味は、「エミリーは私にitの使い方を教えてくれた」となるため、前文に戻ってみると、「I saw a space for bikes 」「私はbikesのためのスペースを見つけた」とあるため、そのスペース(it)の使い方を教えてくれたとわかる。
問4:選択肢のうち、本文の内容と合致する文を選ぶ問題です。
【・答え エ】
正しい内容を選ぶ問題。15行目に「I also saw some kinds of wild birds around the lake」とあるため、エが正解。
アの内容は第一段落に記載あり。しかし、本文にはlast summer と書いてある。問題文ではそれが「この前の冬」となっているため間違い。イの内容は本文に記載なし。問題文には「健太が湖にホストファミリーを連れて行く計画を立てていた」とあるが、本文には、「エミリーがある湖に健太を連れて行く計画をした。」とあるため間違い。
ウの問題文には「健太はポートランドにある湖に行くために午後に自転車に乗って家を出発した」とあるが、本文第二段落には「we left home before noon」「私たちは正午前に家を出た」とあるため、ウは間違い。
問2:「相手の言葉が日本語でない相手と話すとき、あなたはどうするか」という質問の答えのグラフより、2~6年生の「英語で答える」の割合の説明としてふさわしいものを選択する問題です。
【・答え エ】
ア:「2年生は60%を超えており、3年生はそれ以上の割合である」
2年生は59.6%であり、60%を超えていない。したがって不適。
イ:「一学年だけ60%を下回っており、それが最も低い学年である」
60%を下回っている学年は5つある。したがって不適。
ウ:「6年生のその解答の割合は、その学年の半数の人数よりも少ない」
6年生は50.9%であり、6年生の半数の人数よりも多い。したがって不適。
エ:「それぞれの学年はそれより1つ下の学年より割合が低い」
6年生が最も低く、学年の順番に割合が高くなり、1年生が最も高くなっている。したがって、内容に合致する。
問1:選択肢のうち、本文中の空欄①に最も適している前置詞を選ぶ問題です。
【・答え イ】
前置詞選択問題です。期間を表すinが正解です。inの後ろには季節や月、年を示す単語をつけて、その期間全体を表します。
問2:選択肢のうち、本文中の空欄②に最も適している文を選ぶ問題です。
【・答え イ】
前文でBenが「でも、ホストファミリーのところには寒い日に使う良いものがあるんだ」と言っているので、”良いもの”とは何かと訊ねる”What is it ?”が正解です。
問3:下線Ⓐを表している内容を本文中から英語6語で抜き出して答える問題です。
【・答え some nice things used in Japan】
one of themとは「それらのひとつ」という意味なので、それらを表すものがある前文に注目すると、”I found some nice things used in Japan.”と言っているので、上記が答えとなります。
問4:正しい文法となるように[ ]内の語を並べ替える問題です。
【・答え many things that happened】
about(前置詞)の後ろには名詞が来るので、それを修飾するmanyと組み合わせてmany thingsができます。many thingsとは、和文より「その日学校で起きたたくさんのこと」となるので、前の名詞thingsを説明するthatにhappened at school … .を繋げると、文章として成り立ちます。したがって、many things that happenedが正解です。
問5:下線Ⓑを表している内容を本文中から探し、日本語で答える問題です。
【・答え 梅の花を見ることは、春を感じるための良い方法であるということ】
下線Ⓑが含む文章全体を見ると、”I think so too…”となっており、「私もそう思う」という意味になっています。したがって、soの
部分は前文の”seeing ume blossoms…”の部分となり、これを訳すと上記のようになります。
問6:正しい内容になるように、本文中の空欄④に英語3語を記述する問題です。
【・答え have wanted to】
和文に「…以来ずっと…見たいと…」とあるので、ここに現在完了形が入れば文意を満たします。現在過去形はhave + 過去分詞なので、過去分詞に「~したい」であるwanted to をつけると、上記の答えになります。
問7:本文の内容と合致するように、問いに対する答えを英語で記述する問題です。
【・答え ①:Yes, he does. ②:He felt two seasons.】
①:問いは「Benはホストファミリーと使うこたつが好きか?」であり、10行目にBenがI like it very much.(itは文脈よりこたつを表す)と言っているので、問いに肯定する上記が答えとなります。
②:問いは「Benはこたつを使って公園で梅の花を見ていくつの季節を感じたか?」であり、下から5行目にBenがBy using…I felt both winter and spring.と言っているので、「彼は二つの季節を感じた」という英文である上記が答えとなります。
問1:写真について説明する英文を条件1・2を踏まえて記述する問題です。
【・解答例 】
問1:本文中の空欄(a)~(c)にあてはまる動詞をそれぞれ選び、必要があれば適切な形に変えて記述する問題です。
【・答え (a):telling (b):learned (c):covered】
(a):文脈より、「伝える」を表すtellを選びます。for の後なので、動名詞の形であるtellingが正解です。
(b):文脈より、「学ぶ」を表すlearnを選びます。「日本に来る前に、私は日本に4つの季節があることを学びました」となるので、過去形であるlearnedが正解です。
(c):文脈より、「覆う」を表すcoverを選びます。文章の前後を見ると「…赤や黄色の葉で覆われる山々…」となるので、受動態の形であるcoveredが正解です。
問2:下線Ⓐの表している内容を本文中から英語5語で抜き出して答える問題です。
【・答え the four seasons in Japan】
前文に「私は日本に4つの季節があることを学んだ」とあるので、theyは「それら」すなわち「日本の4つの季節」を表します。したがって、上記が正解です。
問3:選択肢のうち、本文中の空欄①に最も適しているものを選ぶ問題です。
【・答え ウ】
前文より、Benは日本の四季の違いを知りたいと思っていたとあり、現在は日本で季節の違いを楽しんでいるとある。従って、Benが今日本の季節についてどう感じているか?を訊ねる「what you think…in Japan」の ウ が正解です。
問4:正しい文法となるように[ ]内の語を並べ替える問題です。
【・答え the seasons you will feel】
あなたが感じるだろう季節という文意を表せばよく、名詞+SVで表せます。名詞の部分には季節であるthe seasonsが入り、SVにはその後にあなたが感じる(だろう) を表すyou will feelを入れます。したがって、上記の答えになります。
問5:本文中の(ア)~(エ)のうちから”It is … haikus.”という文章を挿入する場所として最も適しているものを選ぶ問題です。
【・答え イ】
意訳すると、「これは俳句の決まり事のようなものだ」となります。これが示すのは、イの前文にある”…a haiku contains … the season”なので、イに入ることが分かります。
問6:下線Ⓑを表している内容を本文中から探し、日本語で答える問題です。
【・答え 日本の式にはっきりとした違いがあるので、それぞれの季節を表す季語があるということ】
下線部の文全体を見ると、「季語についてのBenの考えを聞けて良かった」とあります。聞けて良かった、ということはBenの前文にあり、季語について言及しているI think there are … seasons in Japan.を訳すと上記になります。
問7:正しい内容になるように、本文中の空欄③に英語5語を記述する問題です。
【・答え time we spend together around】
和文より、「(こたつの)周りで一緒に過ごす時間」を表す英語が入ればよく、名詞+SVで表します。名詞はtime(時間)、SVにはwe spend together around(周りで一緒に過ごす)と表せるので、上記が答えとなります。
問8:本文の内容と合致するように、問いに対する答えを英語で記述する問題です。
【・答え ①:Yes, they do. ②:Three people will.】
①:問いは「谷先生と真美は梅の花を見る時に春を感じたか?」であり、23,24行目に「春を感じた」と述べられているので、答えは上記のようになります。
②:問いは「次の土曜に真美と一緒に梅の花を見に公園へ行くのは何人か?」であり、文中にBenと谷先生が行きたいと言っているので、3人が行くと分かる、したがって答えは上記のようになります。
問1:選択肢のうち、本文中の空欄①に最も適している前置詞を選ぶ問題です。
【・答え ア】
alongは「~に沿って」という意味であり、walk along the streetで通りを歩くという意味になります。したがって答えはアです。
問2:下線Ⓐの表している内容を本文中から英語6語で抜き出して答える問題です。
【・答え many interesting things about the canal】
some of themより、themの内容は前文にあると推測できます。前文には”I learned many interesting things about the canal”とあり、次の文で「それらについて伝えます」と言っているので、themの内容は上記の答えとなります。
問3:選択肢のうち、本文中の空欄①に最も適している動詞を選ぶ問題です。
【・答え ウ】
make A 比較級で「Aをより~する」という意味になります。今回の文に当てはめるとmake Kyoto more prosperous(京都をより繁栄させる)となり、文意が通ります。
問4:本文中の空欄③に、その前後の意味が繋がるような英文の順序となっている選択肢を選ぶ問題です。
【・答え エ】
ⅰは「彼らはまた、疎水から運ばれた水で農家を支援しようとしていました。」
ⅱは「例えば、主な目的は船で多くのものを運ぶことだった」
ⅲは「それを計画した人々は疎水(canal)をいくつかの目的で使用しようとしていました。」
となります。文意より、ⅲ→ⅱ→ⅰだと分かるので、答えはエとなります。
問5:本文中の空欄④に最も適している英語1語を記述する問題です。
【・答え between】
空欄の前後を確認してみると、前にはthe distance、後ろにはthe west end and the east endとなっているので、距離の事を言っているのだと分かります。ここで、amongとbetweenが選択肢になりますが、ここでは2つのものを対象としているので、betweenがあてはまります(amongは3つ以上の時に使われます)。したがって、betweenが正解です。
問6:正しい文法となるように[ ]内の語を並べ替える問題です。
【・答え not such a long tunnel】
文脈より「このとき、日本にこれほどの長さのトンネルは無かった」という文が出来ればいいと分かります。まず、そんな長さのトンネルは無かったという事を表すので、there was notとなります。次に、such + a + 形容詞○○ + 名詞△△で「こんなに○○な△△」と表せるので、これに語を当てはめるとsuch a long tunnelとなります。したがって、上記の答えになります。
問7:指定された日本語に合うように、本文中の空欄⑥に英語を記述する問題です。
【・答え I want more people to visit】
和文に合うように作文する問題です。もっとを表すmoreに気を付けて記述すれば、そこまで難しくないと思います。
問1:選択肢のうち、本文の内容と合致する文を選ぶ問題です。
【・答え ア・オ】
ア:「健二が前の8月に京都に住む祖母を訪ねた時、彼女は疎水について語った後に彼を琵琶湖疎水の博物館に連れて行った。」
1~5行目にそのような記述があるので、内容に合致する。
イ:「健二は、疎水の博物館へ行く前に、琵琶湖疎水建設の主任技師について知っていた。」
12~13行目に「博物館に行くまで知らなかった」という記述があるので、不適。
ウ:「健二にとって、琵琶湖疎水のデザインは最も興味深いことの一つである。何故なら外国の技師によって作られたからである。」
11,12行目に「この疎水のデザインと建設は日本人技師によってなされた」という記述があるので、不適。
エ:「田辺朔郎(Tanabe Sakuro)は琵琶湖疎水で発電するという決定がされた後、発電について研究する為にアメリカへ送られた。」
下から8~6行目に「彼が帰国した後、疎水を利用した発電をすることが決定された」という記述があるので、不適。
オ:「健二は明治時代に琵琶湖疎水を計画した田辺朔朗や他の人々の素晴らしい働きを知ることができて良かった。」
下から3~2行目にそのような記述があるので、内容に合致する。
問2:「相手の言葉が日本語でない相手と話すとき、あなたはどうするか」という質問の答えのグラフより、2~6年生の「英語で答える」の割合の説明としてふさわしいものを選択する問題です。
【・答え エ】
ア:「2年生は60%を超えており、3年生はそれ以上の割合である」
2年生は59.6%であり、60%を超えていない。したがって不適。
イ:「一学年だけ60%を下回っており、それが最も低い学年である」
60%を下回っている学年は5つある。したがって不適。
ウ:「6年生のその解答の割合は、その学年の半数の人数よりも少ない」
6年生は50.9%であり、6年生の半数の人数よりも多い。したがって不適。
エ:「それぞれの学年はそれより1つ下の学年より割合が低い」
6年生が最も低く、学年の順番に割合が高くなり、1年生が最も高くなっている。したがって、内容に合致する。
問1:写真について説明する英文を条件1~3を踏まえて記述する問題です。
【・解答例 】
問1:選択肢のうち、最も適しているフレーズを選ぶ問題です。
【・答え イ】
make A(名詞)+B(形容詞)の語順で「AをBにする」と表せます。これに則しているのはイのto make the air in the room cleanだけです。(the air in the roomで一つの名詞句となっています)。
問2:選択肢のうち、最も適しているフレーズを選ぶ問題です。
【・答え エ】
A want B to C で「AがBにCしてほしい」と表します。この文章の場合、先生が生徒に学んで欲しいという事を表したいので、Bにthe studentsが、Cにlearnが入ります。学びたいことはhow to act …になるので、the students to learn how to actとなっているエが正解です。
問3:選択肢のうち、最も適しているフレーズを選ぶ問題です。
【・答え ア】
エ:the quickly.は文法より×。ウ:solved by ~(~により解決する)の後に続くcaused the choice quickly.という言い回しは無い(意味も通じない)為、不適。イ:by the causedは文法(語順)より×。ア:The problems caused by the choice were solved quickly.(その選択が原因で発生した問題はすぐに片付いた。)となり、文意が通る。したがってAが正解。
問4:選択肢のうち、最も適しているフレーズを選ぶ問題です。
【・答え ウ】
ア:the more ~,the more ~.という表現はあるが、この文には他の比較表現が無い。inの文法も適さない為、アは不適。
イ:アと同様にthe more ~があるが、文法より不適。
エ:livingは比較表現のない形容詞。more livingという表現は無い為、エは不適。
ウ:animals living in the forest is moreとあり、下線部がanimalsの説明をしている。Showing …forestが一つの名詞句となり、isに自然に繋がる。したがって、ウが正解。
問5:選択肢のうち、最も適しているフレーズを選ぶ問題です。
【・答え イ】
文全体の後半に、very cheerfulとなっているので、文の主語はthe childとわかる。したがって、ウ、エは不適。
アはI metの次にheldが入ってしまっている。これは文法より×。したがって、答えはイとなる。
問6:選択肢のうち、最も適しているフレーズを選ぶ問題です。
【・答え ウ】
問1:本文中の(A)~(D)のうち”The children … lower grades.”という文章を挿入する場所として最も適しているものを選ぶ問題です。
【・答え ア】
Aの後にHowever …と入っているが、そのままでは文脈が微妙です。そこに”The children … lower grades.”を入れると文意が通ります。したがって、Aの選択肢であるアが正解です。
問2:「相手の言葉が日本語でない相手と話すとき、あなたはどうするか」という質問の答えのグラフより、2~6年生の「英語で答える」の割合の説明としてふさわしいものを選択する問題です。
【・答え エ】
ア:「2年生は60%を超えており、3年生はそれ以上の割合である」
2年生は59.6%であり、60%を超えていない。したがって不適。
イ:「一学年だけ60%を下回っており、それが最も低い学年である」
60%を下回っている学年は5つある。したがって不適。
ウ:「6年生のその解答の割合は、その学年の半数の人数よりも少ない」
6年生は50.9%であり、6年生の半数の人数よりも多い。したがって不適。
エ:「それぞれの学年はそれより1つ下の学年より割合が低い」
6年生が最も低く、学年の順番に割合が高くなり、1年生が最も高くなっている。したがって、内容に合致する。
問:選択肢のうち、最も文全体の意味をなす順番となるものを選ぶ問題です。
【・答え ウ】
A:「気候は木々に影響を与え、科学者は木の年輪からその影響を見つけることが出来る。木の年輪から、科学者たちは毎年の天候がどうであったかを推測することが出来る。」
B:「もし逆の状態であったら、木はしっかり育たなかったかもしれない。冷たく乾燥しているとき、年輪は大きくならない。したがって、もし年輪が幅広くないとき、科学者はその年の天候は木にとって厳しかったと推測することが出来る。」
C:「気候はその地域の天候の平均的な状態を表す。科学者たちは様々な手段によって地球の気候についての数多くの情報を収集してきた。過去の地域の気候を研究するために、木を利用する者もいる。なぜ彼らは木を気候の研究に用いるのだろうか?」
D:「だから、彼らは研究に木を利用する。次の例では彼らの気候の推測方法を示す。もし、暖かく、木が十分に水を得ることが出来れば、木は一般的には良く育ち、年輪は幅広くなる。なので、もし年輪が幅広いならば、科学者たちはその年は暖かかったのだと推測できる。」
これらより、C→A→D→Bとなるので、答えはウである。
問1:選択肢のうち、段落2の内容として正しいものを選ぶ問題です。
【・答え エ】
段落2では博物館の外に置かれた陶製の製品は日光や風雨、人の手に晒されても色が落ちることがないという事象から、陶磁器の特性の利用例について述べている。したがって、エが正解。
問2:選択肢のうち、下線①の表している内容について述べられたものを選ぶ問題です。
【・答え ウ】
屋外に展示された名画の複製品は色を落とすことが無いと述べられている。したがって、ウのsome replicas of great paintingsが正解。
問3:選択肢のうち、段落3の内容として正しいものを選ぶ問題です。
【・答え イ
ア:描画は粘土製のパネルを作ってからすると述べられているので、不適。
ウ:熱すると色やサイズが変化すると述べられているので、不適。
エ:粘土を手に入れるのが困難であるとは述べられていないので、不適。
イ:段落3では陶製のレプリカを作成することの困難さと、高い技術を持った人が必要であると述べられている。したがって、正解はイ。
問4:選択肢のうち、段落4の内容として正しいものを選ぶ問題です。
【・答え 】
ア:重要な壁画を発見する為に正確なレプリカが必要である、とは述べられていないので、不適。
ウ:日本の歴史学者は壁画を保護しようとしていると述べ手られているので、不適。
エ:本当の壁画は陶製の複製品が作られる前に傷ついてしまったとは述べられていない。したがって不適。
イ:壁画の精密な複製品は陶製のパネルで作られていると述べられている。したがって、正解はイ。
問1:選択肢のうち、琵琶湖疎水の建設についての文章中の説明として正しいものを選ぶ問題です。
【・答え ア】
イ:「若い日本人技師にはとても難しかったので、外国人技師によってなされた」
日本人技師によって建設されている。したがって不適。
ウ:「田辺朔朗が1883年に主任技師になった後、二年間建設が止まった」
建設自体が1885年に始まったので、止まっていたわけではない。したがって不適。
エ:「1890年に完成した時ときには、既に建設開始から20年が経過していた。それは建設がとても困難であったからである」
建設開始から5年で完成している。したがって不適。
ア:「琵琶湖疎水の建設は、疎水から水を運ぶことによって京都の産業を促進する為に計画された」
本文中に述べられているので、正解はア
問2:本文中の(A)~(D)のうち”However,…used today.”という文章を挿入する場所として最も適しているものを選ぶ問題です。
【・答え ウ】
文意が通るのはCしかない。したがって、Cの選択肢であるウが正解。
問3:選択肢のうち、本文中の空欄①に最も適している前置詞を選ぶ問題です。
【・答え イ】
空欄の前後を確認してみると、前にはthe distance、後ろにはthe west end and the east endとなっているので、距離の事を言っているのだと分かります。ここで、amongとbetweenが選択肢になりますが、ここでは2つのものを対象としているので、betweenがあてはまります(amongは3つ以上の時に使われます)。したがって、betweenが正解です。
問4:選択肢のうち、本文の内容と合致するものを選ぶ問題です。
【・答え ア】
ア:農家への水の供給は琵琶湖疎水建設の一つの目的だった。
本文中の内容に合致する。したがって正解はア
イ:1883年の日本に2400メートルを超えるトンネルがあった。
1883年に2400メートルを超えるトンネルが無かったと述べられている。したがって不適。
ウ:竪坑を用いたトンネル建設手法は1885年より前に既に用いられていた。
この建設で初めて用いられたと述べられている。したがって不適。
エ:「琵琶湖疎水は琵琶湖から2世紀もの間水を運んできた」
125年以上とあり、200年以上はたっていない。したがって不適。
問1:選択肢のうち、空欄①に入れたときに文意に合う単語を選ぶ問題です。
【・答え イ】
イを挿入し、「ホタルのいくつかの種はsynchronization をみせる良い例である。」とすればよい。
問2:本文中の(A)~(D)のうち”Through … become similar.”という文章を挿入する場所として最も適しているものを選ぶ問題です。
【・答え ウ】
問題文の文章「しかしながら、明治時代には、今日使われている高い技術をもっていなかった」という内容を、Cに挿入すると、「疏水を設計するために、建設のための土地の調査をする必要があった。」→問題文の文章「しかしながら、明治時代には、今日使われている高い技術をもっていなかった」となり、→「だから、土地を調査することと、疏水を設計することは難しかった」となり、意味が通る。
問3:”The fireflies”に続く文として、本文の内容と合致するものを選択肢から選ぶ問題です。
【・答え イ】
2つ地点の間をあらわす際によく用いられる「between A and B」の表現を使う。
問4:選択肢のうち、空欄②で説明すべき文としてふさわしいものを選ぶ問題です。
【・答え ア】
アの「農業者への水の供給は琵琶湖疏水を作る目的の1つだった」という内容は、本文序盤に記載あり。
問1:選択肢のうち、下線①の表している内容について説明しているものを選ぶ問題です。
【・答え ア】
下線①のthemの直前にある「several chemical substances」を受けていると考えると自然に意味が通る。
問2:本文中の(A)~(D)のうち”Also, this means … substance”という文章を挿入する場所として最も適しているものを選ぶ問題です。
【・答え イ】
問題文の「また、これは人々がたくさんの種類の匂いを化学物質の合成から作り出すことができることを意味する」をbに挿入すると自然な意味になる。
問3:選択肢のうち、下線②を表している内容として正しいもの選ぶ問題です。
【・答え ウ】
下線部②の文章は「新しい合成により生じる匂いは甘いoneで、人々は気分が良くなる」となるため、oneにはウが最適。
問4:選択肢のうち、空欄③に入れるのに最もふさわしい単語を選ぶ問題です。
【・答え エ】
本文で匂いと人々の記憶の関係が触れられているためエが適切。
問:「将来『一つの分野で飛びぬけた技能を持った人』と『幅広い分野で高い技能を持った人』のどちらになりたいか」について、自分の意見とその理由、その人物像になってやりたいことを記述する問題です。
【・解答例 】
問題内容の概要は、1つの特定の分野において特に高い技能を持つ人間と、様々な分野において高い技能を持つ人間とがいる。将来どちらのタイプの人間になりたいか?はじめにあなたの意見と理由を書き、その後にそのあなたが選んだタイプの人として将来なにがしたいか書け。というもの。答えは人それぞれだとは思うが、英作文のコツとして1つ言えることは、問題文の表現をうまく利用することだ。これはさまざまな英作文問題で役に立つから実践してほしい。あくまで一例として軽く英作文しておく。
I want to be a type of person who has high skills in various fields. The type of person might be able to enjoy many kinds of jobs and grow up mentally through those a lot of experiences. That’s why I want to be the type of person more than another type of person. In the future, I want to keep trying other fields without being satisfied with myself as the type of person.
家庭教師のやる気アシストは、大阪府にお住まいの受験生のお子さんを毎年たくさん指導をさせ頂き、合格に導いています。
おかげさまで、昨年度の合格率は、関西エリア全体で97.3%という結果を残すことが出来ました。
高い合格率の秘訣は、指導経験豊富な先生の指導力に加え、1対1の指導でお子さん一人ひとりの状況に合わせた、お子さんだけのカリキュラムで勉強が進められるから!
家庭教師のやる気アシストは、お子さんの志望校合格まで全力でサポートさせて頂きます!
お子さんにとって「成果が出る勉強法」ってどんな勉強法だと思いますか?
お子さんそれぞれに、個性や性格、学力の差もあります。そんな十人十色のお子さん全員に合う勉強法ってなかなかないんです。
たからこそ、受験生の今だけでもお子さんだけの勉強法で受験を乗り越えてみませんか?
やる気アシストには、決まったカリキュラムはありません。お子さんの希望や学力、得意や不得意に合わせて、お子さんだけのカリキュラムで指導を行っていきます。また、勉強法もお子さんそれぞれに合う合わないがあります。無料体験授業では、お子さんの性格や生活スタイルを見せていただき、お子さんにとって効率的な成果の出る勉強のやり方をご提案させて頂きます。

