






発達障害のお子さんは社会生活を送ることに対して困難を覚えることがあります。
健常者では簡単なことでも苦痛に感じることがあり、健常者でも苦痛なことはより苦痛に感じてしまいます。
社会生活と聞くと買い物や他者とのコミュニケーションなどが一番に挙げられますが、それ以外にも髪を切りに行く・歯医者に行く・役所に行くなども社会生活の一部です。
子どもの頃はできなくても、親が先立ち1人になった時(福祉的な支援があるとはいえ)にできなければならないと困ります。
少しずつでも練習していかないといけません。
そこで、大人になる前から身につけておきたい社会生活についてお話していきます。
人間誰しも必ず一度は病院にお世話になるでしょう。
風邪でも歯医者でも骨折でも、何か体が傷つくことがあれば病院に行くことになります。
その病院に慣れておかないと、恐怖で行くことができなくなり、重大な病気になっていても処置ができなくなり取り返しがつかなくなる…ということもあります。
そうならないためにも、小さいときから病院になれさせるようにしましょう。
大人でも病院が苦手な人もいるので、それを子どもに強制するのは難しいと思います。
しかし、大人のように「なんだか熱っぽいから病院に行って薬をもらってこよう」ということを障害者は認識しにくいです。
「風邪を引いたら病院に行く」「具合が悪い時はお医者さんに診てもらう」ということを子どもの頃から教えておくことで、実際に具合が悪くなったときに病院に行くという選択肢ができます。
また、病院も雰囲気で一気にトラウマになってしまう可能性もあるので、最初の病院選びは慎重にしましょう。
病院内が明るい・先生が優しそうなども選ぶ基準にしてもいいと思います。
初めてかかる病院には予約などする際に「発達障害があるので配慮して欲しい」ということを伝えておくことをおすすめします。

昔は「甘やかしているから」と医者側からも言われていましたが、近年は発達障害の認知も増えてきているので、配慮をしてくれる病院も多くなってきています。
病院がトラウマになっていけなくなってしまうと大人になってから困ってしまうので、慎重にいきましょう。
発達障害のお子さんは感覚過敏がある子どもが多いです。


服のタグが気になる
化学繊維の服が着れない
タートルネックが苦手
など、、。特に首周りに感覚過敏を持つ傾向にあります。
そのため、髪を切ることを苦手としている子どもも多いです。
ハサミが首元や耳に当たるのが怖くて苦手、ということなのでそれに慣れさせる必要があります。
事前に自宅で準備できることは、髪を切るとどうなるか・どんなことをするのかを絵に描いて説明しましょう。
余裕があれば絵本のような形で見せることができるといいです。
そこで何を使って髪を切るのか・どこからどのように切るのかなどを描いておくと見通しを立てて確認することができます。
実際に人形を使って髪を切る真似事をするのもわかりやすいと思います。
そして、実際に美容室に行ってみます。
美容室には予め電話で発達障害があり感覚過敏でハサミが苦手であることを伝えておいて、今まで見せていた内容に沿った工程で切ってもらう(髪を洗う・髪を切る・髪を乾かすなど)ようにします。
お店側からすると迷惑かもしれませんが、お子さんのためにも理解ある美容室を選びましょう。
髪を切ってもらうところを見ていたほうが安心するという場合もあるので、子どもに確認しながら切っていきます。



終わったらたくさん褒めてあげて、ご褒美を用意しておきましょう。
途中でパニックになってしまったら無理やり進めずに終わりにしましょう。
またできそうなタイミングで切りにいき、少しずつ慣れさせましょう。
日常生活で必要になるのが買い物です。
福祉サービスを使ってヘルパーさんと買い物に行くこともできますが、基本的なお金の管理は本人になります。
買い物のサポートもしてもらえますが、自分である程度できていないといけません。
まず、家で買い物ごっこをして買い物やお金に慣れる練習をします。
100円ショップにあるお金のおもちゃよりも実際のお金でやったほうがわかりやすいです。
何度も繰り返して買い物ごっこをして練習をして、次はスーパーやコンビニなどで買い物をする練習をします。
例えば、、、
➀300円以内で買い物をする


②金額に応じた小銭を出す


そういったことを繰り返していくと、自然と買い物ができるようになってきます。



今はICカードなど現金じゃなくても買い物ができて便利ですが、やはり現金でないと買い物ができない場所もあるので、現金にも慣れておきましょう。
発達障害があっても社会で生きていくことは変わりなく、自分でできるようになる必要があります。
身体障害者が自立して生活ができているように、発達障害者でも自立できます。
小さい頃からの慣れがあるかないかで大人になってからの自立生活が変わってきます。地道に少しずつ慣れていきましょう。
発達障害をお持ちのお子さんは、お子さんによってそれぞれの特性がありますので、個別指導塾よりもマンツーマン指導で住み慣れたご自宅で勉強することができる家庭教師は学習効果が出やすい傾向にあります。
まずは、お気軽に体験授業をお試しいただき、アシストとの相性をご確認下さい!
発達障害があるなしに関わらず、お子さんの特性に合わせて勉強を教えていくことが成績アップややる気づくりには欠かせません。マンツーマンで指導をする家庭教師では、その特徴を最大限に活用しながらお子さんの得意を伸ばすことができると考えています。
やる気アシストでは、検査を受けたお子さんに関しては、その結果をもとに担当の家庭教師と一緒に指導方針や指導内容を工夫しています。もちろん、検査を受けていないお子さん、発達障害の診断がでなかったいわゆる「グレーゾーン」のお子さんに関しても、お子さん一人ひとりに合わせた指導をしていくことに変わりはありません。
お子さんの発達面で気になることや心配なことがあればお気軽にご相談ください。専門のスタッフがこれまでの経験や知識をもとに、お子さんにぴったりのやり方をアドバイスさせていただきます!
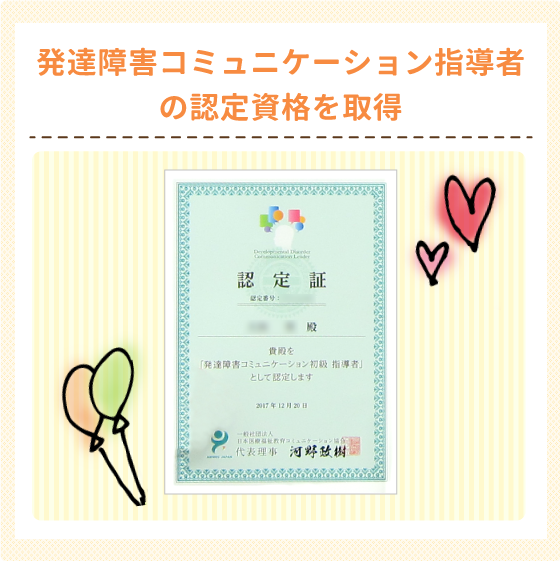
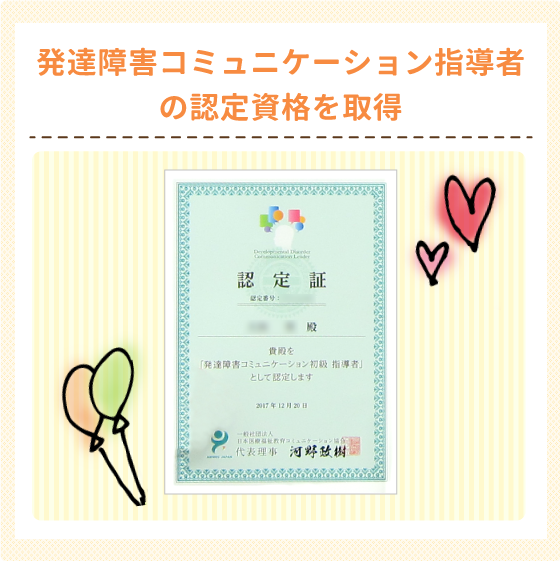
発達障害コミュニケーション指導者の資格は、発達障害に関する正しい知識で、お子さんをサポートできる公的な認定資格です。
発達障害に関する基礎的な知識、関わり方の基本などを発達障害の専門的な知識を持つスタッフが、よりお子さんの個性に合わせた指導ができるよう、家庭教師の指導サポート・指導を行っています。
発達障害に関する正しい知識を持つスタッフが、お子さんの特性を見極め、指導する家庭教師の選定から行うことでより適切なサポートができる体制を整えています。
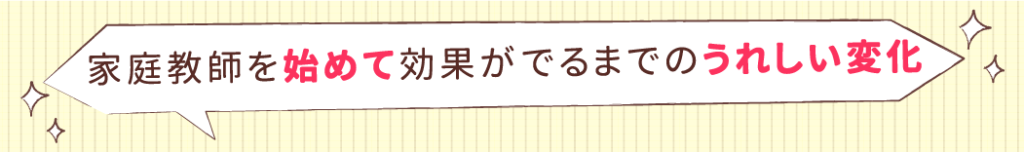
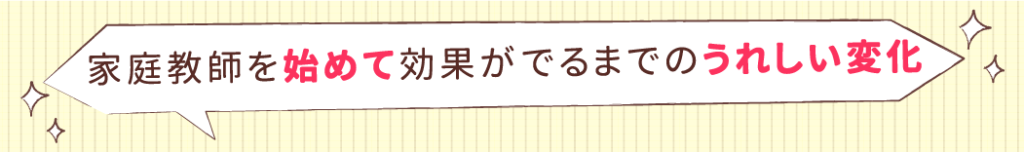
将来や受験について前向きに!
[かなちゃん中学2年生(不登校)]
来年度は受験生になるかなちゃんは、明るく誰とでも仲良くなれる性格のお子さんですが、学校での人間関係が原因で半年前から学校へ・・・


家庭教師で大幅に成績アップ!
[あやなちゃん小学5年生(ADHD)]
小3の後半あたりから、宿題をしないことが増えてきたあやなちゃん。勉強嫌いも徐々にひどくなっていきました。普段からお子さんの・・・



