






子どもの気温感は難しいもので、大人が思っている以上に暑く感じたり寒く感じたりします。
言葉が発せない乳児の頃などは様子を常に気にして服を着せたり靴下を脱がせたりしますが、言葉が分かるようになると自分で「暑い」「寒い」などと言うことができるので、こちらも対処しやすいです。
しかし、発達障害児になると気温感を掴むことができず、小学生になっても自分で気温の調整をするために服の着脱や気温に合わせた服を選ぶことが難しいです。
どうしたら気温感を掴むことができるようになるのか、どうしたら自分で気温に合わせた服を選べるようになるかについてお話していきます。
インターネットで「服装 気温表」などと検索すると、気温に合わせた服装の表が出てきます。
インターネットには「20度:薄手の長袖か半袖に薄いものを羽織る」「5度:ダウンジャケットやコートが必要」などが書かれているので、天気予報を一緒に見て「今日は20度だから薄いものを着ようか」と話すことができます。
発達障害児にとって一番苦手なのが抽象的な内容を理解するということです。
「何となく暑そうだから半袖を着る」「気温は高いけど雨だから薄いものを着る」ということが苦手です。
そのため、「この気温のときはこれを着よう」というルールを決めることで、最終的に自分で気温に合わせた服を選べるようになります。
最初はこちらが服を持ってきて「今日は○度だからこれを着ようか」と持っていき、それに慣れてきたら一緒に気温表と天気予報を見て「今日はどれにする?」と決めて、それもできてきたら自分1人で決められるようにします。

中学生になると制服になり、気温に関係なく冬服・夏服なので自分で選ぶということが少なくなりますが、週末の服装を自分で選べるようになります。
気温表は部屋の見やすいところに貼っておいて、いつでも見れるようにしましょう。
アニメやドラマでは季節に応じた服装をしています。
夏が舞台のドラマでは半袖を着ていますし、冬が舞台のドラマではコートを着ています。
それを見て「夏は半袖を着る、冬はコートを着る」という認識を持たせます。
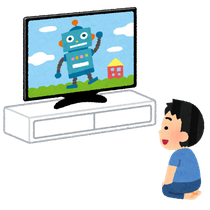
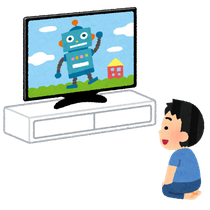
子どもにアニメやドラマを見せすぎると良くないと言われますが、こういった要素もあるので一概に見せないほうが良いというわけでもないです。
「このアニメ、みんな半袖だけど暑いのかな?夏なのかな?」など話を振ることで、気温感を覚えるきっかけにもなります。
アニメやドラマだと服装以外にも食べるものが季節に応じているので、そこを見るのもいいでしょう。
「かき氷食べてるね、夏だね」「温かい鍋が食べたいって、冬だね」「さつまいもや栗の料理だね、秋なのかな?」など振ることで、気温に対する興味も持たせることができます。



こう考えてみると、アニメやドラマには季節に関するヒントが多く隠されています。
子どもが興味を持ったアニメやドラマも教材になるので、内容が過激でなければ見せてあげて会話の取っ掛かりにするのもいいと思います。
気温表を見たりアニメの中の季節感を見るのも気温感を覚える方法ではありますが、やはり根本は本人の体温の感覚を身に着けさせるのが必要です。


頬を触って暑そうだったら「これは暑いだよ、暑いときは涼しい服を着ようね」手を触って冷たかったら「手が冷たいね、これは寒いだから暖かいコートを着ようね」と体温の様子を見て「このときはこうしようね」という話をします。
外に出て「夏だね、夏は暑いね」「雪が降っているよ、今日は冬だから寒いね」と、植え付けていきます。
すぐに理解するのは難しいかもしれませんが、体感して何度も繰り返していくと次第に分かるようになり、「今日は暑いかな?寒いかな?」と話を振って答えを待つような会話にも持っていけます。
もし、気温感がまだ掴めずに暑い日に長袖を着てしまっても「長袖が良かったかな?でも暑いから半袖にしようね、自分で選べたのは偉いね」と頭ごなしに否定せずに、やんわりと間違いを直してあげましょう。



「暑いのに長袖なんて着ないで!」と否定してしまうと自己肯定感が低くなってしまい、こちらの顔色をうかがって自分で服を選べなくなって困ってしまいます。
時間はかかりますが、声掛けなどに気をつけて感覚を養っていきましょう。
気温感を養うことは熱中症や凍傷などの予防にもなります。
大人が「今日はこれを着ようね」と勝手にあてがってあげるのは楽ですし時間もかからずに準備できます。
しかし、子どもの頃はそれで良くても大人になってから自分で服を選べなくなってしまうので、将来的には子ども自信が困ってしまいます。
時間がかかり面倒な手順を踏むことになりますが、朝起きる時間を早くする・天気予報のときには天気予報だけ見られるようにルーティンを組むなど工夫をするとスムーズに行うことができます。
学校のある日が難しければ、週末にやるのも一つの方法です。少しずつ身に着けていけるようにサポートしましょう。
発達障害をお持ちのお子さんは、お子さんによってそれぞれの特性がありますので、個別指導塾よりもマンツーマン指導で住み慣れたご自宅で勉強することができる家庭教師は学習効果が出やすい傾向にあります。
まずは、お気軽に体験授業をお試しいただき、アシストとの相性をご確認下さい!
発達障害があるなしに関わらず、お子さんの特性に合わせて勉強を教えていくことが成績アップややる気づくりには欠かせません。マンツーマンで指導をする家庭教師では、その特徴を最大限に活用しながらお子さんの得意を伸ばすことができると考えています。
やる気アシストでは、検査を受けたお子さんに関しては、その結果をもとに担当の家庭教師と一緒に指導方針や指導内容を工夫しています。もちろん、検査を受けていないお子さん、発達障害の診断がでなかったいわゆる「グレーゾーン」のお子さんに関しても、お子さん一人ひとりに合わせた指導をしていくことに変わりはありません。
お子さんの発達面で気になることや心配なことがあればお気軽にご相談ください。専門のスタッフがこれまでの経験や知識をもとに、お子さんにぴったりのやり方をアドバイスさせていただきます!
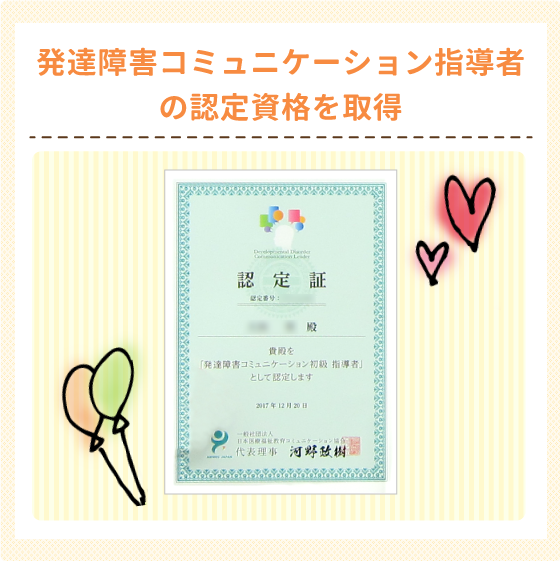
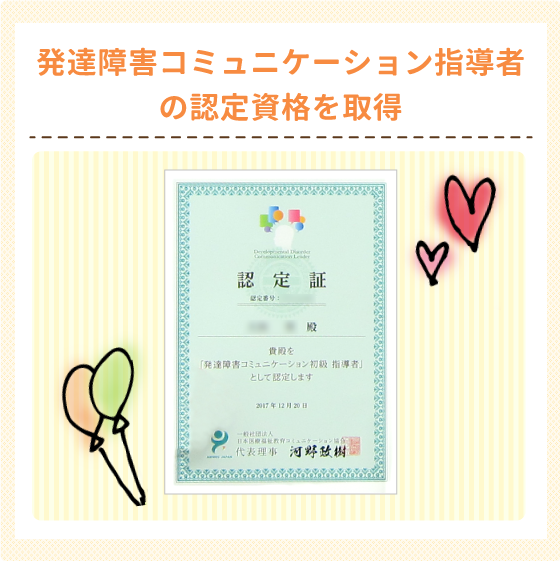
発達障害コミュニケーション指導者の資格は、発達障害に関する正しい知識で、お子さんをサポートできる公的な認定資格です。
発達障害に関する基礎的な知識、関わり方の基本などを発達障害の専門的な知識を持つスタッフが、よりお子さんの個性に合わせた指導ができるよう、家庭教師の指導サポート・指導を行っています。
発達障害に関する正しい知識を持つスタッフが、お子さんの特性を見極め、指導する家庭教師の選定から行うことでより適切なサポートができる体制を整えています。
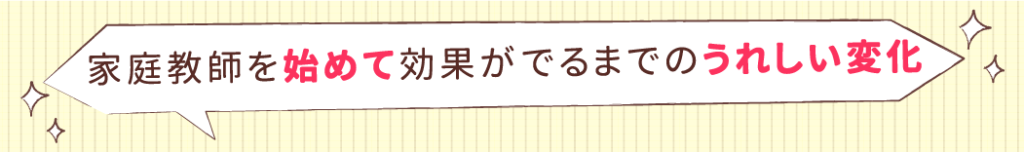
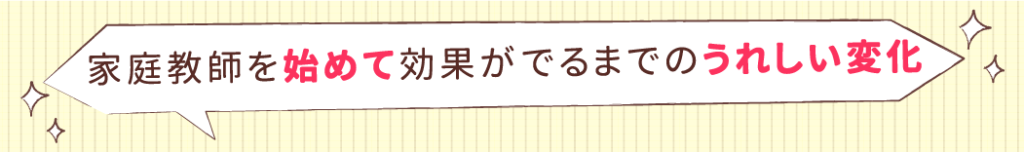
集中力アップ!やる気アップ!
[つばさくん小学6年生(ADHD)]
小学校低学年のころから、学校の授業に集中できないことや宿題を忘れてしまい注意されることが多く、5年生になったとき先生に・・・


苦手な事にもチャレンジするように!
[ちづるちゃん中学1年生(LD)]
学習障害の中でも「読字障害」の傾向が強く、文字を読むことを特に苦手にしています。文章を読むのに時間がかかってしまうので・・・



