






発達障害のお子さんがいる家庭では、どうしても子どもが中心の生活になります。
健常児であれば0歳から保育園に通わせることもできますし、その時間に働くこともできますし、一緒に出かけたり遊んだりコミュニケーションをとって会話を弾ませることもできます。
しかし、発達障害児であると保育園や幼稚園に通わせるのも一苦労で、仕事をすることもままならないでしょう。
出かけたりするのにも癇癪やパニックを考えると躊躇してしまう部分があると思います。
子どもが一人だけならまだ生活がぎりぎり回ると思うのですが、ここに健常児の兄弟がいると、兄弟を放置してしまいがちになります。
最近では兄弟に障害児がいることを「きょうだい児」「ヤングケアラー」などと言います。
あまりいい表現ではないのですが、そう思われないようにしていかなければなりません。
兄弟に発達障害がいるお子さんへの接し方、その時に発達障害のお子さんにはどうしていけばいいのかをお話していきます。
障害児の兄弟は周りから「将来はお兄ちゃん・お姉ちゃん(弟妹)のお世話をするんだね」と言われがちです。
親がそういうつもりでなくても、「家族の問題は家族で解決するものだから」という意識がある人ほどそういったことを言ってきます。
「親の介護するんでしょ?」という話に近いものがあります
親として将来どうしていくべきか、子どもが小さいうちから考えていかなければなりません。
確かに兄弟の支援は必要な場面が出てきます。
例えば
学校の登下校で一緒に行ってもらったり、学校の連絡事項を代わりに聞いてもらったり、遊び相手になってもらったり、、、
しかし、それがいつまで続くのかを考える必要があります。
登下校で面倒を見てもらうのは何年生までか、世話を見てもらうのは何歳までか、障害のある方が高校を卒業したらどうするのか、早い段階で決めておかないと兄弟自身が将来像が見えずに苦しみます。
そして早い段階で決めたことを兄弟にしっかりと伝えましょう。

「お兄ちゃんも一人でできることを増やしていきたいから、お手伝いはあまり頑張らなくていいよ」と言ってあげるだけでも兄弟のプレッシャーは少なくなります。
そして、同時に障害児にも「自分でできることを増やそうね」と身の回りのことから自分でできるように教えていかなければなりません。
障害があると色々とハンデが出てきます。
発語や発育の遅れがあるため、どうしてもそちらに意識がいきがちです。
着替えなどの身の回りのことが一人でできるようになるのにも時間がかかりますが、健常児は比較的早い年齢で身の回りのことができるようになってきます。
第一次反抗期、いわゆるイヤイヤ期が2歳辺りにくるのだが、「一人でやりたい」と思うことから自分で身の回りのことをやるようになっていく。
しかし、発達障害のお子さんはその傾向が薄いこともあり、自分でできるようになるまでに時間がかかる。
そのため、兄弟のほうがいつの間にか一人でできるようになっていて、しっかり者に育つことがあります。
親としてはしっかり者に育ってくれるのはたいへんありがたいことだと思います。
しかし、それは「親に甘えたいけれど兄弟につきっきりだから甘えられない」ということにもなります。
障害があるからつきっきりになるのは仕方ない部分もありますが、兄弟のほうにもしっかり目を向けてあげましょう。
障害児の着替えに手を出すのであれば、兄弟には一緒に服を選んであげるなど、アプローチの仕方は違っても同じように接して親と過ごす時間を作ってあげましょう。



障害児に特別につきっきりになる時間が多くなってしまうのであれば、一日だけ兄弟と過ごす時間(いきたいところに連れて行く、おもちゃを買ってあげるなど)も作るのが大切です。
障害のあるないに関係なく平等に同じ時間を作ってあげてください。
兄弟に障害児がいるといじめの対象になりかねません。
子どもなので障害について理解できず「お前の兄ちゃんなんで変な言葉喋ってるの?」「お前の弟と会話できないんだけど頭悪いの?ばか?」と心無いことを言ってくることがあります。
これは止めようにも止めることが難しいです。
しかし、兄弟に「お兄ちゃんのことで嫌なことを言われるかもしれないけれど、友達にどう話す?」と前もって聞いて確認することができます。
「苦手なことがあること、できることもあること、本人は頑張っていることをしっかり話せるようにしよう」と強く立ち向かう練習も必要です。



友達にからかわれるのはとても辛いと思います。しかし、友達と話せるのは親ではなく子ども自身です。
自分の言葉で兄弟の障害のことを話せるようにすることも、接し方の一つです。
発達障害児が兄弟にいると窮屈に感じることが多くあります。
それをできるだけ取り除いてあげるのも親の役目です。
兄弟がいると配慮することも多いですが、同じように平等に接してあげてください。
発達障害をお持ちのお子さんは、お子さんによってそれぞれの特性がありますので、個別指導塾よりもマンツーマン指導で住み慣れたご自宅で勉強することができる家庭教師は学習効果が出やすい傾向にあります。
まずは、お気軽に体験授業をお試しいただき、アシストとの相性をご確認下さい!
発達障害があるなしに関わらず、お子さんの特性に合わせて勉強を教えていくことが成績アップややる気づくりには欠かせません。マンツーマンで指導をする家庭教師では、その特徴を最大限に活用しながらお子さんの得意を伸ばすことができると考えています。
やる気アシストでは、検査を受けたお子さんに関しては、その結果をもとに担当の家庭教師と一緒に指導方針や指導内容を工夫しています。もちろん、検査を受けていないお子さん、発達障害の診断がでなかったいわゆる「グレーゾーン」のお子さんに関しても、お子さん一人ひとりに合わせた指導をしていくことに変わりはありません。
お子さんの発達面で気になることや心配なことがあればお気軽にご相談ください。専門のスタッフがこれまでの経験や知識をもとに、お子さんにぴったりのやり方をアドバイスさせていただきます!
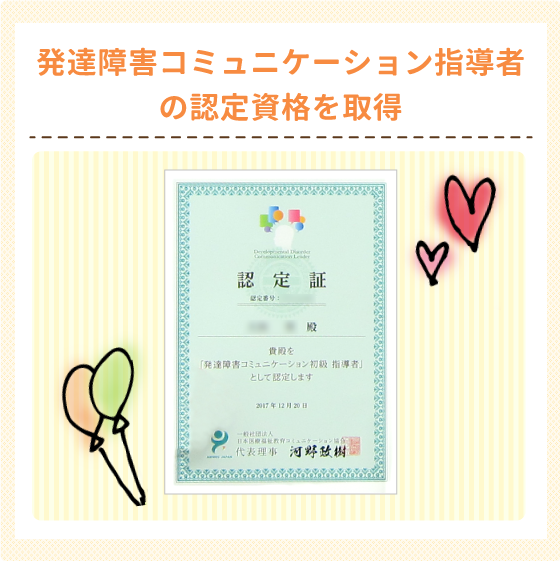
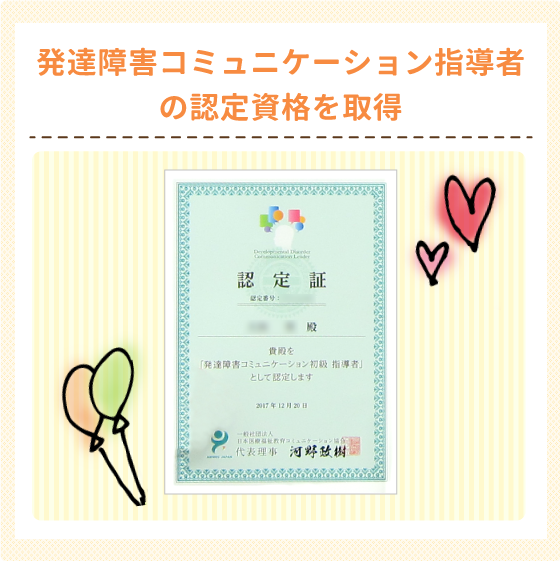
発達障害コミュニケーション指導者の資格は、発達障害に関する正しい知識で、お子さんをサポートできる公的な認定資格です。
発達障害に関する基礎的な知識、関わり方の基本などを発達障害の専門的な知識を持つスタッフが、よりお子さんの個性に合わせた指導ができるよう、家庭教師の指導サポート・指導を行っています。
発達障害に関する正しい知識を持つスタッフが、お子さんの特性を見極め、指導する家庭教師の選定から行うことでより適切なサポートができる体制を整えています。
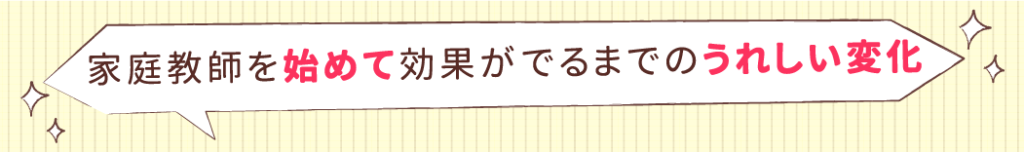
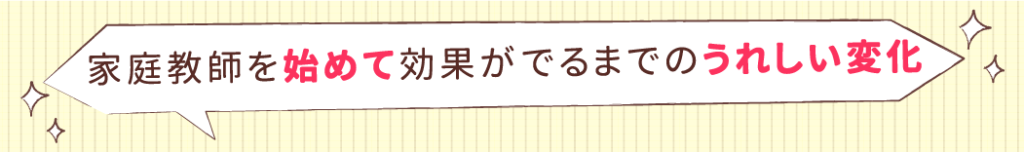
自分に合う勉強法が見つかった!
[ゆうくん中学2年生(LD)]
小学校の時に学習障害の診断を受けていて、文字(特に漢字)を書くことに困難があります。漢字を書くことが特に多い国語は・・・


苦手克服で自信とやる気がアップ!
[みゆちゃん小学4年生(LD)]
学習障害と診断を受けており、学習面で特に計算が苦手で算数障害の傾向が強いお子さんです。小学校入学当初から苦手で・・・



