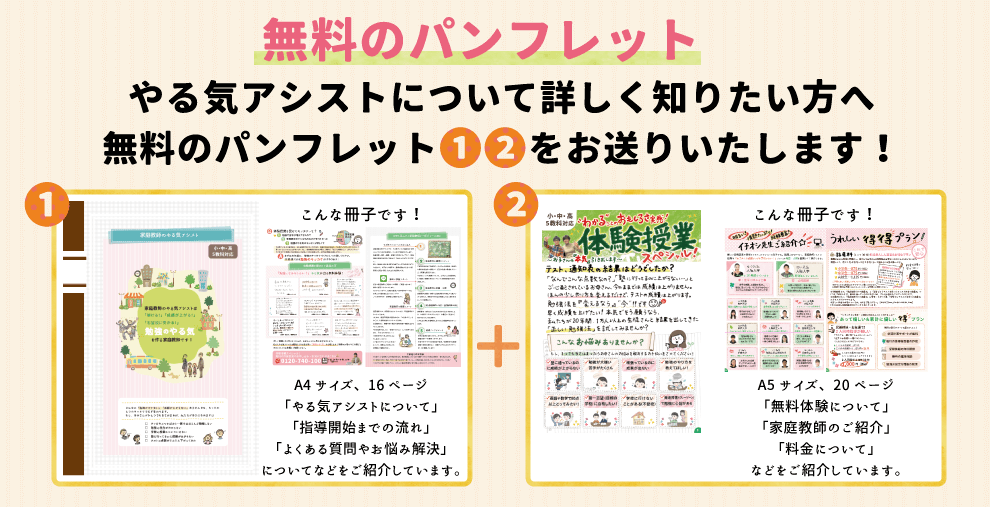息子が学校に行きたがらなくなってから、私たち親子の日常は大きく変わりました。彼が明るく元気な笑顔を見せなくなり、朝の登校が憂鬱な戦いになってしまったのです。息子が不登校になった理由を知らずに、私は心配と共に深い悲しみを胸に抱えていました。
3年生になってしばらく立った頃5月の終わりくらいでしょうか。
前兆は朝からでした。まず、朝なかなか起きて来ない。次に登校班に遅れ始めました。
この時点で私は成長期だし、眠かったりするのだろうと安易に考え、特に気にせずそのうち持ち直すだろうと安易に考えていました。
ある日、学校から職場に電話がありました。「息子さんが来ていないんです」。
私はその報告に動揺しつつも、たしかに家を出発した旨を伝え、校内を探してもらうことにしました。心配しつつ連絡を待っていると「息子さんトイレにいました。お腹が痛かったみたいです。」との連絡。「心配して損したわ、まったく!」なんて教師に軽口を叩いて電話を切ったのですが…それから似たような報告を何度も受けることに…。
今思うとこの時点で、朝の息子の表情が暗くなっていた事に気づくべきでした。
その後の報告はどうしてこんな事に?と思うことの連続。登校班からはぐれ、学校途中の公園のトイレにこもったり、校庭の隅でうずくまっていたりと、とにかく学校に着くまでの途中で、まるでかくれんぼの様に、息子は朝遅刻し続けるようになりました。
こうなると流石の私も心配になります。ある日、私は息子に向き合い、「学校に行きたくない理由は何なの?」と尋ねました。彼はしばらく黙った後、「先生が苦手なんだ」と小さな声で答えました。「怒ってばかりで、話を聞いてくれない」と。普段人の悪口を言うことのない息子のその言葉に、私は胸が痛くなりましたが、彼の気持ちを知ることができて少しホッとしました。それに息子が不登校になった理由を教えてくれたことで、少なくとも親子の距離はまだ保たれていると感じられました。私は息子の変化に気づくことが遅れてしまったことを誤り、なぜそう思うようになってしまったのかなど話を聞くことに終始し、翌日の学校は、遅刻せずに登校していきました。話を聞いてあげたことで、少しスッキリ出来たのかなと思います。
確かに参観の時に見かけた担任の先生は、厳格そうで、ルールにも厳しそうな人だなという印象がある方でした。息子の言い分だけでは、単純にルールを守れていない息子が叱られているだけの様にも思いましたし、息子が学校に行きたがらなくなるという大変な事態に陥ってしまったわけですから、迷いましたが担任の先生に連絡を取り、話をすることにしました。こちらの窮状を伝え、対応策が出ればと思いました。
しかし結果は残念なもので、担任は対策の提案をしてくれるわけでも、アドバイスをくれるでもなく、ひたすら、「自分は正しい」「親も一緒になってみっともない」「しつけが悪い」というようなことを言われ、面食らってしまい、ショックのため自宅に帰ってからボロボロと涙が…みっともないですね。
私は息子に学校に行きなさいとはもう言えませんでした。本当はしっかりと担任と話して、指導が愛情であることを引き出し、息子に向き合い、先生の立場を伝えて話し合いの場を持ち、教師なりの愛情について諭して、学校生活に戻ってもらいたかった。他の先生にも相談したかったのですが、力のある先生だったこともあり、結局泣き寝入り状態でした。学校という場は、教育機関でもありますが、親にとっては子どもを人質に取られているも同然で、強く出ることが出来ないものなのです。
結局その後、とうとう息子は学校へ行けなくなり、担任の任期期間の4年生いっぱいまで、多くを自宅で過ごしました。
息子の不登校の原因が担任だったことは最悪ですが、その先生の任期が終わり、他校へ移動となった5年生からは、息子は学校に通うようになりました。そして、ある日の朝、息子が「学校に行くの、今日は楽しみだな」と笑顔で言ったのです。その瞬間、私の胸には喜びと感動が込み上げました。
一般的に教師が偉そうだと感じる子どもの気持ちには、様々な要因が絡んでいますが、今回のように、教師が子ども達に対して上から目線で接したり、感情を無視するような態度を示したりすると、子ども達の反感を招くことがあります。子ども達が教師に対して偉そうに感じることは、成長過程において自然な感情です。教師もそれを理解し、子ども達の立場や気持ちに寄り添うことが大切です。子ども達が安心して学び成長できるよう、教師は教育の現場で常に子ども達とのコミュニケーションを大切にし、共感や理解を示す姿勢を持つことが重要です。
私はこの様な事例を、教育者の皆さんにぜひ知ってもらいたい。そして、ぜひ自身を振り返ってみて欲しいです。
そして同じ様に不登校になってしまった保護者さまには、まずは子供の気持ちに寄り添い、理解しようとする姿勢が大切だと伝えたい。
そしてカウンセリングや専門家の支援を受けながら、子供の心の健康を優先し、自分自身もサポートを求めることが重要です。学校とのコミュニケーションを大切にし、柔軟な学習環境を探求することで、子供の成長と自信の回復を支えましょう。
これからも私は、息子が直面する様々な困難を共に乗り越え、彼に寄り添える親であり続けたいと思っています。彼の未来が輝かしいものになるよう、私は彼のそばに寄り添っていきます。
やる気アシストでは学校へ行くことができていないお子さんを多数任せていただいています。
不登校のお子さんは一人でいる時間がほかのお子さんよりも圧倒的に長くなり、必然的に孤独感を感じやすくなります。
また、お子さんが学校にいけないことで、勉強への不安やストレスを感じることもあるかと思います。高学年になってくると「勉強しなければ」という気持ちが強く、焦りや不安が募ってくるお子さんもいらっしゃいます。
アシストでは、このようなお子さんに寄り添い共感することでお子さんの孤独を回避しながら、お子さん1人ひとりにあった方法で少しずつ生活に勉強を取り入れていくところからスタートしていきます。
お子さんの勉強の習熟度に合わせたカリキュラムで「わかる」を引き出し自信や自己肯定感を高めていけるよう指導を行っていきます。勉強の習慣付けではお子さんの自主性を引き出すためにも、決して指示や過度なアドバイスはしません。
「できるところ」「得意なところ」から伸ばしていく指導で、達成感・充実感を感じてもらいながらお子さんが前に進めるようにそっとサポートをしていきます。
また、家庭教師の勉強法は、学校の授業のようにみんなが同じ内容を学習するというような指導ではなく、お子さんの様子を見ながら、分からない所・苦手・テストに出る箇所などお子さんにとって強化すべきポイントを集中学習することができるので、学校や塾に比べ、効率的に学習を進めていくことが可能です!
不登校の間、学校の勉強を両親が付きっ切りで見てあげたり、お子さんを面と向かって褒めるということはなかなか難しいというご家庭も多いです。家庭教師が間に入り、力になれることがあるかもしれません。不登校でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください!

やる気アシストでは、ひきこもり支援相談士・不登校訪問専門員の認定資格を取得し、不登校のお子さんをより深く理解し、寄り添い、正しい知識を持って指導に当たれる体制づくりに力を入れています。
認定資格を持つスタッフが中心となり、社内スタッフや家庭教師に向け、不登校の正しい知識をつけるための勉強会や指導を行っています。
また、不登校のお子さんを持つご家族の方に向けても、接し方や声掛けの方法などをお伝えさせて頂いており、ご好評いただいております。
不登校のお子さんは第三者として接することができる家庭教師という存在が大きな役割を果たすことが多いです。私たちアシストは、正しい知識を持った家庭教師が、お子さんの「やる気」や「自信」を引き出しながら、勉強面だけでなく、精神面でもお子さんの良き相談相手になれるよう、お子さんに寄り添いながら指導を行っていきます。
体験授業では、同じようなお子さんを教えたことのある経験豊富なスタッフがお伺いして、ご家庭の要望やお子さんの希望をお聞きした上でぴったりの方法を一緒に考えていきます。
また、実際に指導が始まった後も気になることや心配なことがあれば、お電話にて専門スタッフが相談をお受けすることも可能です!
不登校は早期に対応することが大切です。具体的な質問や相談が無くても大丈夫!「不登校になってしまって不安…」といった曖昧なご相談でOK!
まずはお子さんのためにお早めにご相談ください!