






感情のコントロールは健常者でも難しいときがあります。
犯罪などでも「イラッとしたからやった」「相手の発言が気に入らなかった」など、感情がコントロールできれば防げたのでは?という内容があります。
健常者でさえ感情のコントロールが難しいのですから、障害者も難しいです。
更に、発達障害だと対人関係のトラブルが多いので、ふとした相手の発言で相手に暴力をふるってしまったり自分自身を傷つけてしまったりなど、感情を抑えられればどうにかなったのではないかということがあります。
健常者にも難しい感情のコントロールを発達障害者だとどのように対処していくのかについてお話していきます。
人によってイライラの具合は違います。
あまり気にならないくらい・・・。
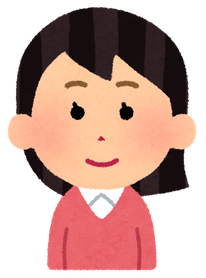
Aさん
つい手が出てしまうぐらい、我慢できない!
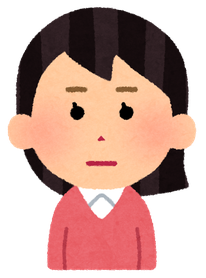
Bさん
と、人によって「ちょっと」の具合が違います。
そのため、AさんがBさんから「ちょっとイライラするんだよね」と言われても「あまり気にならないくらいか」と捉えてしまうと、認知のズレからトラブルに発展してしまいます。
また、発達障害児は「ちょっと」「まあまあ」などの抽象的な言葉を自分の中で理解するのが苦手なことが多いので、より一層トラブルに繋がります。
そこで、イライラを数値化することをしてみましょう。
度合いが1から10まであるなかでどのくらいなのかを教えてもらうことで、どのくらいのイライラ度なのかを知ることができます。
そのため、「今イライラ度が6くらい」と教えてもらうと「今少し興奮状態なのかな、落ち着かせるために好きなことをさせようかな」と対応することができます。

数値化が難しければ、子どもの好きなもので例えてイライラの数値化を図ります。「どのくらい大きなプリン?」「マリオのブロックどのくらい壊したい?」など、具体的なもので数値化することができます。
数値化できればこちらも対応がしやすいので、子どもの発達や認知能力に合わせてイライラ度の数値化をしてみましょう!
人や自分を傷つけない方法でイライラを発散する手段を身に着けましょう。
発達障害児はイライラを発散する方法が分からず、自分で溜め込み、ふとしたことがきっかけで爆発することがあります。
そのため、イライラを発散する手段を見つけて爆発しないようにしていきます。
例えば、紙に嫌なことを書き出して破り捨てる、パンチングマシーンを使う、好きなものを食べたりゲームをするなど、様々
紙に嫌なことを書き出すのはイライラすることを言語化しているので、最終的に冷静になることもできます。
そして破り捨てることで爽快感を得ることができます。
新聞のチラシの裏やいらないプリントなど紙とペンがあればできるので、たまに行うのにはいいでしょう。
パンチングマシーンもかなりストレス発散になります。
壁や物を殴ってしまうと傷ついて後が大変ですが、パンチングマシーンは殴ることが目的になっているので、問題ありません。
机の上に乗るくらいの大きさのものも売られているので、通販などで買うこともできます。



ストレス発散はものに当たるだけでなく、食やゲームなどに向けるのもいいです。毎日のようにイライラしたから食べて発散する・ゲームを長時間やるなどをすると生活リズムや健康などに支障が出るので、適度に行うようにしましょう。
色んなストレス発散の方法を組み合わせて、ストレスフリーで過ごせるようにしましょう。
今まではイライラを上手に発散する方法をお話してきました。
もう少し上手になるためには、イライラしていることを言語化できるようになるといいです。
イライラしていることを言語化することで、文字で見て冷静になれることを目的としています。
最初は前述のようにとにかく紙に書きなぐって大まかに言語化します。
慣れてきたら「何が嫌なことなのか」「何が悪いのか」「どうしたいのか」など項目を設けて書いてみます。
これらの項目を書いた紙を用意して随時書けるようにしておきます。
書いた内容に怒ることはしないようにしましょう



イライラするきっかけは人それぞれなので、それを咎めてしまうと「これはいけないことなんだ」と自分の中に溜め込んでしまって、イライラを発散できず爆発することに繋がってしまいます。
書いた内容に対して「これにイラッとしたんだね」と受け止めるようにして、共感すると「自分のことをわかってもらえた」と安心し、感情も落ち着いてきます。
感情のコントロールは本当に難しいです。健常者の大人でも難しいのですから、子どもで発達障害であればもっと難しいです。
しかし、訓練していくと徐々に感情をコントロールすることができ、他人や自分を傷つけることなく過ごすことができます。
時間はかかってしまいますが、ゆっくりと子どものペースに合わせてやっていきましょう。
発達障害をお持ちのお子さんは、お子さんによってそれぞれの特性がありますので、個別指導塾よりもマンツーマン指導で住み慣れたご自宅で勉強することができる家庭教師は学習効果が出やすい傾向にあります。
まずは、お気軽に体験授業をお試しいただき、アシストとの相性をご確認下さい!
発達障害があるなしに関わらず、お子さんの特性に合わせて勉強を教えていくことが成績アップややる気づくりには欠かせません。マンツーマンで指導をする家庭教師では、その特徴を最大限に活用しながらお子さんの得意を伸ばすことができると考えています。
やる気アシストでは、検査を受けたお子さんに関しては、その結果をもとに担当の家庭教師と一緒に指導方針や指導内容を工夫しています。もちろん、検査を受けていないお子さん、発達障害の診断がでなかったいわゆる「グレーゾーン」のお子さんに関しても、お子さん一人ひとりに合わせた指導をしていくことに変わりはありません。
お子さんの発達面で気になることや心配なことがあればお気軽にご相談ください。専門のスタッフがこれまでの経験や知識をもとに、お子さんにぴったりのやり方をアドバイスさせていただきます!
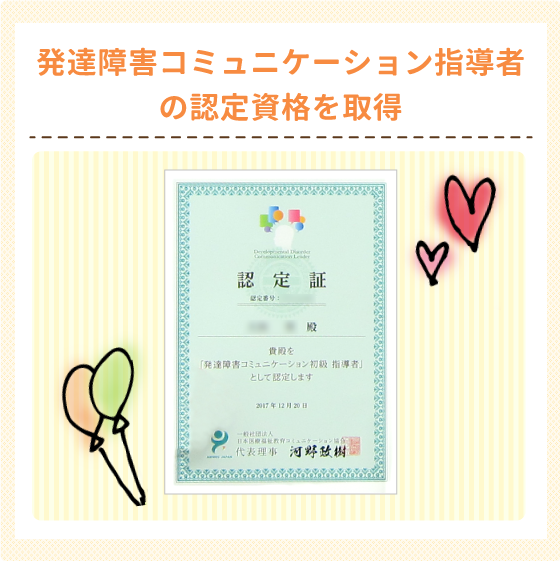
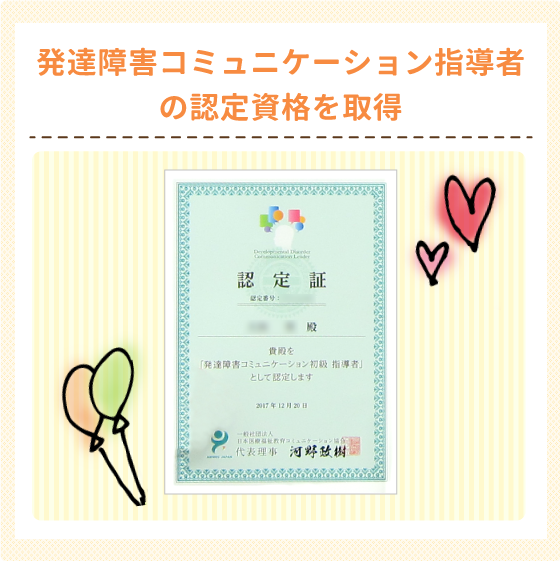
発達障害コミュニケーション指導者の資格は、発達障害に関する正しい知識で、お子さんをサポートできる公的な認定資格です。
発達障害に関する基礎的な知識、関わり方の基本などを発達障害の専門的な知識を持つスタッフが、よりお子さんの個性に合わせた指導ができるよう、家庭教師の指導サポート・指導を行っています。
発達障害に関する正しい知識を持つスタッフが、お子さんの特性を見極め、指導する家庭教師の選定から行うことでより適切なサポートができる体制を整えています。
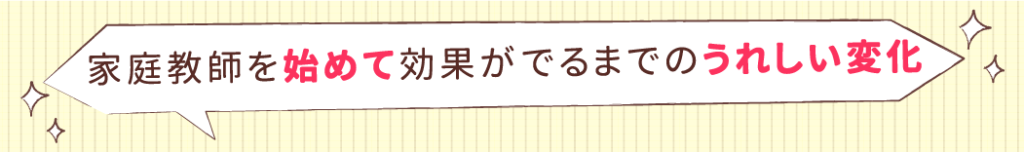
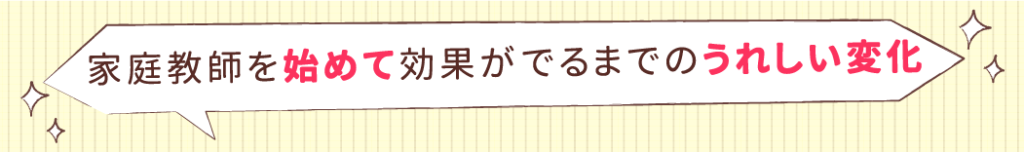
苦手な事にもチャレンジするように!
[ちづるちゃん中学1年生(LD)]
学習障害の中でも「読字障害」の傾向が強く、文字を読むことを特に苦手にしています。文章を読むのに時間がかかってしまうので・・・


自分に合う勉強法が見つかった!
[ゆうくん中学2年生(LD)]
小学校の時に学習障害の診断を受けていて、文字(特に漢字)を書くことに困難があります。漢字を書くことが特に多い国語は・・・



