






特別支援学校や特別支援学級に入学すると、保護者と担任の先生との連絡のやり取りが多くなります。
しかし、どのくらいの頻度で連絡をして良いのか、何を連絡すれば良いのかがいまいち分からず、何となくで連絡をとる保護者の方もいます。
学校と家庭での様子を総合して子どもへの接し方を考えていかなければならないので、家庭での様子はしっかりと伝えていかなければなりません。
そこで、今回はどのくらいの頻度で・どのような内容で先生と連絡を取り合っていくのかについて、お話していきます。
特別支援学校・学級に入ると必ず連絡帳のやり取りを行います。
学校からは「今日の授業での様子」「生活の様子」など学校での生活全般について書かれてきます。
その家庭版が家庭からの連絡帳です。
学校から帰ってきてどう過ごしているか・食事はきちんと摂っているか・宿題などはやっているかなど、生活面での報告が必要になります。
学校 給食を食べている
家庭 食事をまともに食べない
学校 おとなしい
家庭 暴力的
など、、、、そういった学校とは違う点を連絡帳に書くことで、学校側がカウンセラーを用意してくれたり面談を設定してくれたりします。
もちろん何もなければ日常のことを書きましょう。
何となく気になることがあれば連絡帳に書いて報告することもできます。
また、就寝時間と起床時間を書くこともあります。
自分の部屋がある子どもは「もう寝るね」と言っても部屋でずっと起きていることもあります。
そのため、部屋に入って少し経ったら本当に寝ているかどうか確認して連絡帳に書き込むのもいいでしょう。

「寝るね」と宣言した時間で寝ているはずなのに学校でずっと眠そうにしていると他の病気を疑ってしまうため、なるべく正しい時間を書き込めるようにしましょう。
基本的に連絡帳でのやり取りになりますが、どうしてもすぐに気になることや「これはかなり様子がおかしい」という疑念が出てきたら、電話でのやり取りをおすすめします。
「家に帰ってきて泣き出した、何があったのか聞いても答えてくれない」など、心配なことがあればすぐに聞きましょう。
また、連絡帳で話しても解決しきれない問題なども、電話で聞いたほうが早いこともあります。
例えば、前述で「給食は食べるのに家では食事を取らない」ということがあったとします。
最初は連絡帳で報告しますが、なかなか改善しないようであれば先生に相談する意味で電話をしてもいいと思います。
「改善しないのでどうにかできないか、カウンセラーに相談などできないか」と真剣に話すと、学校側も真剣に相談に乗ってくれます。



ただし、童話のオオカミ少年と一緒で、真剣な内容でないときにしつこく電話すると本気で連絡を取りたいときに流されてしまう可能性もあるので、本当に心配なときにだけ電話連絡をするようにしたほうがいいです。
先ほどはこちらから学校側に連絡することについてお話しました。
学校側も同じように保護者に直接確認したいことなどがあります。
そういったときにいつでも連絡をしてきても良いように最初に伝えておきましょう。
もちろん仕事などで出られない時間帯もあると思いますが、出られる時間帯やLINEなどにメッセージを入れてもらうなど、いつでも確認できるように工夫をしましょう!
緊急事態はいかにスピーディーに連絡を取り合えるかが大切になってきます。



常に携帯を気にしなければならないので仕事に集中できなかったり、携帯が鳴っただけで焦ってしまったりと気が気でない時間が多くなると思います。
何事もなければホッとして終わることができます。
障害がある子どもを育てるのであればどうしても避けられない道だと思って割り切るしかありません。
発達障害を持つお子さんを育てるためには学校と家庭での連係プレーが必要になります。
連係プレーをスムーズにするためには学校と家庭の信頼関係が必要になってきます。
いきなり電話でやり取りするのは難しいと思います。
そのため、最初は連絡帳でしっかりとやり取りをしていき、学校行事にも積極的に参加して先生との信頼関係を築いていって、いつでも連絡をとれるようにしていくことが連係プレーへの第一歩です。
学校と家庭が気軽に連絡を取れる関係になれれば、いつでも子どもの変化に気づくことができますし、それに対しての策も考えることができます。
連絡を密に取っていき、子どもがストレスなく楽しく生活できるように学校と協力していきましょう。
発達障害をお持ちのお子さんは、お子さんによってそれぞれの特性がありますので、個別指導塾よりもマンツーマン指導で住み慣れたご自宅で勉強することができる家庭教師は学習効果が出やすい傾向にあります。
まずは、お気軽に体験授業をお試しいただき、アシストとの相性をご確認下さい!
発達障害があるなしに関わらず、お子さんの特性に合わせて勉強を教えていくことが成績アップややる気づくりには欠かせません。マンツーマンで指導をする家庭教師では、その特徴を最大限に活用しながらお子さんの得意を伸ばすことができると考えています。
やる気アシストでは、検査を受けたお子さんに関しては、その結果をもとに担当の家庭教師と一緒に指導方針や指導内容を工夫しています。もちろん、検査を受けていないお子さん、発達障害の診断がでなかったいわゆる「グレーゾーン」のお子さんに関しても、お子さん一人ひとりに合わせた指導をしていくことに変わりはありません。
お子さんの発達面で気になることや心配なことがあればお気軽にご相談ください。専門のスタッフがこれまでの経験や知識をもとに、お子さんにぴったりのやり方をアドバイスさせていただきます!
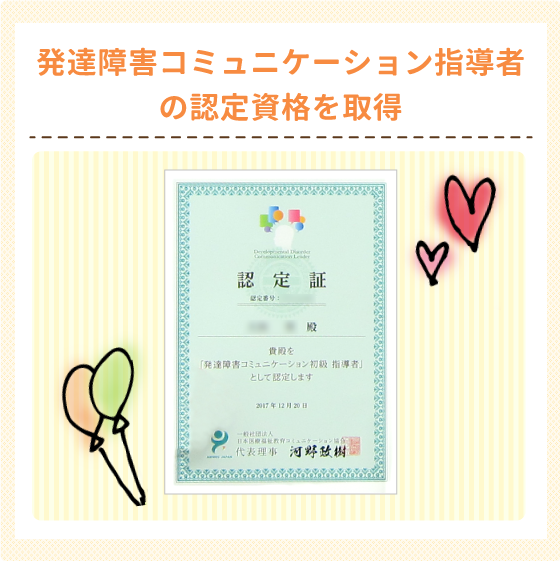
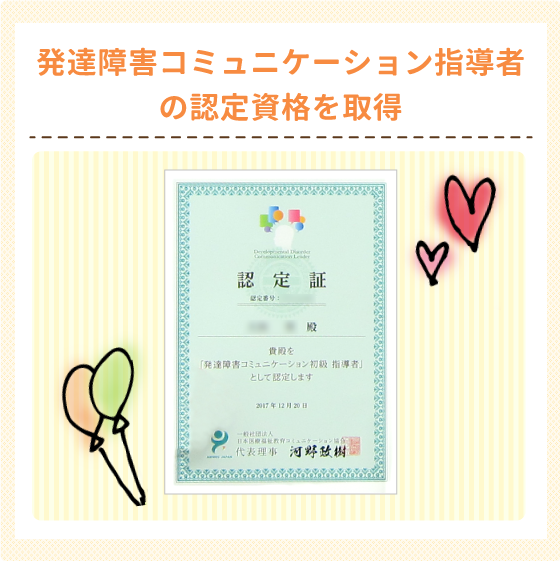
発達障害コミュニケーション指導者の資格は、発達障害に関する正しい知識で、お子さんをサポートできる公的な認定資格です。
発達障害に関する基礎的な知識、関わり方の基本などを発達障害の専門的な知識を持つスタッフが、よりお子さんの個性に合わせた指導ができるよう、家庭教師の指導サポート・指導を行っています。
発達障害に関する正しい知識を持つスタッフが、お子さんの特性を見極め、指導する家庭教師の選定から行うことでより適切なサポートができる体制を整えています。
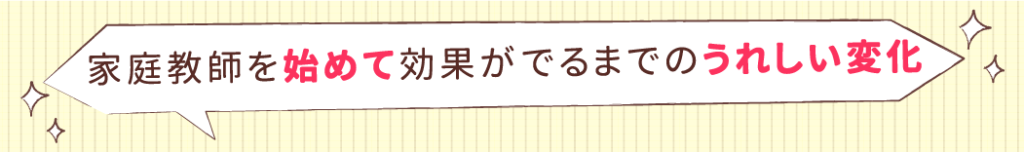
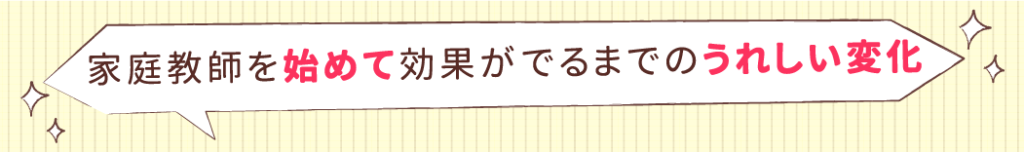
予習のやり方をマスター!
[りりかちゃん中学1年生(ASD)]
小学生の時の発達検査で軽度のアスペルガー症候群と診断されています。小学校では通級に行っていましたが、中学に上がってからは普通学級で・・・


将来や受験について前向きに!
[かなちゃん中学2年生(不登校)]
来年度は受験生になるかなちゃんは、明るく誰とでも仲良くなれる性格のお子さんですが、学校での人間関係が原因で半年前から学校へ・・・



