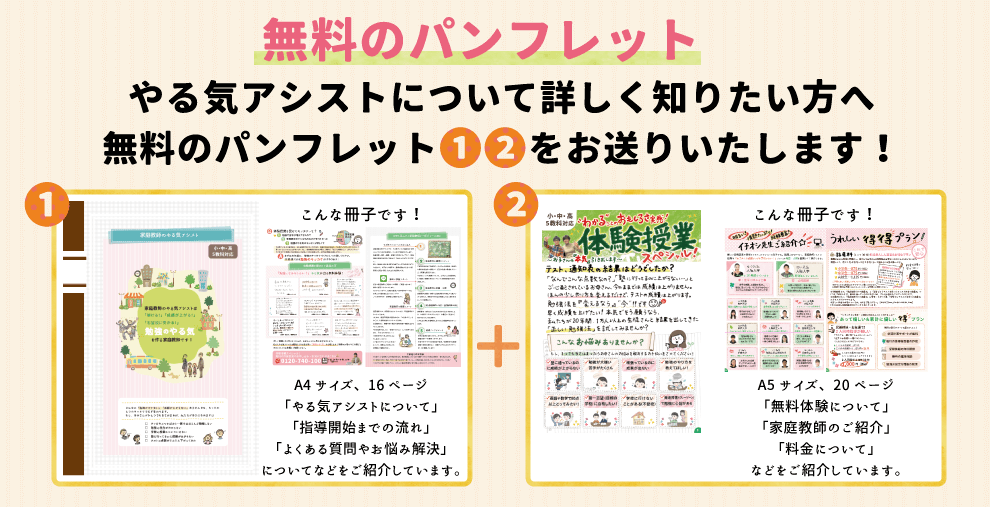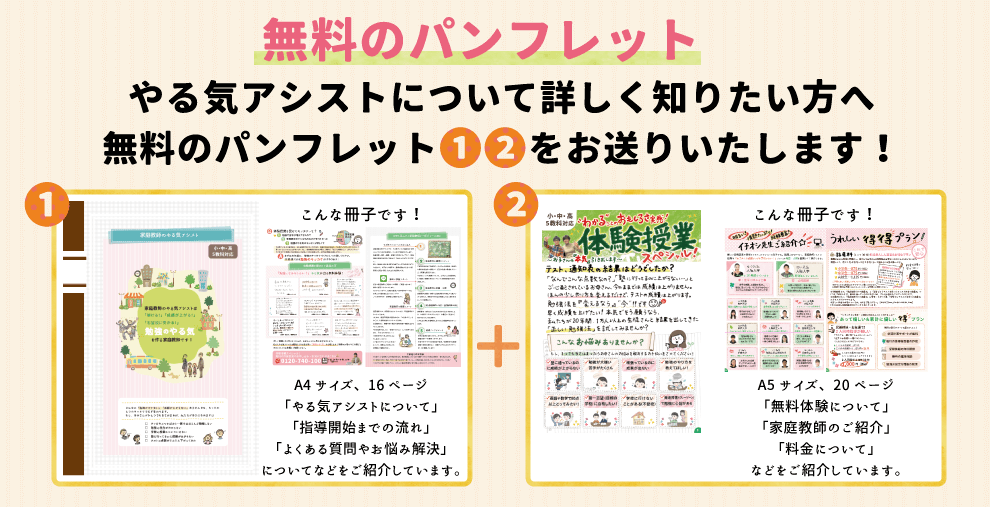不登校期間中にゲームにハマってしまう子どもは少なくありません。
子どもが不登校になってから、「ゲームばっかりで部屋に引きこもっている」「夜中までゲームをやっていて昼夜逆転の生活になっている」「このままゲームにハマってしまって社会に出られなくなるのでは?」不登校の子どもを持つ親の中にはこのような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
ゲームそのものが悪いのではありません。
ゲームにハマってしまう背景を明らかにするとともに子どもが上手にゲームと付き合えるようにすることが大切です。
この記事では、不登校の子どもとゲームの上手な付き合い方について解説し、親はどのように子どもと向き合えば良いかを考えます。
親にとって一番悩ましいのが、「ゲームを取り上げるべきか」であると思います。
しかし、結論からお伝えすると、親の判断で取り上げることは逆効果だということです。
ゲームを取り上げてみたはいいものの、親子関係が悪化した、かくれてゲームをやるようになった、部屋に引きこもるようになった、といったことはよくある話です。
強制的に禁止するのではなく、親子で納得できるルールを作ることが重要です。
また、特に人気のあるオンラインゲームはインターネットを繋いでオンライン上の仲間とチームになって対戦するという特徴があります。
ゲームの話題で友達とコミュニケーションを取れるようになった、というケースはよくある話であり、一概にゲームが悪い影響を与えるわけではないということは強調しておきたいです。
ゲームの中のコミュニティが本人にとっての居場所になっていることもあります。
このようなケースでは、学校での人間関係が上手くいっていないということも考えられます。
子どもがゲームにハマってしまい、困っているという親の中には勝手に親のお金を使い込んでいるというケースもよくあります。
近頃、小中学生に流行っているゲームは一度本体とソフトを買えば楽しめるものというよりも、スマートフォンなどのアプリケーションを通して無料で始められるものが多いです。
無料で始められるものの、課金をすることで強くなるため、親のカードを使って勝手に課金するといったケースもあると言われています。
このような場合、親も冷静にはなれず、事態を重く受け止めて厳しく叱るのは当然です。
しかし、子どもがそこまでの行動をしてしまった背景を知ることが大切です。
なぜ勝手にカードを盗んで課金したのかと追及するのではなく、お金の使い方について話し合うことが重要です。
お小遣いの範囲内で課金する、それ以上の金額を課金したい場合は、手伝いをしてお小遣いを稼ぐ、といったルールを作ることが有効である場合が多いです。
そうすることで、課金する金額が減ったりゲームの時間を減らすことができるだけでなく、他の活動もすることができます。
何か手伝いをした場合は、「ありがとう」「助かっているよ」といった声をかけることも大切です。
感謝されることで「またやろう」という気持ちになれるだけでなく自己肯定感も上がります。

さらに、例えば子どもが1万円をゲームに課金したとして、「1万円稼ぐためにはどのくらいの労働が必要なのか」「同じ1万円でちょっと豪華なものが食べられるんだよ」といった具体的なものと比較して親子で考えるという方法もあるでしょう。
ゲームに関するルールを作るという考えが一般的だと思います。
しかし、ゲームはアニメや漫画とは違い、時間制限を設けてプレイができるものではありません。
「良いところだったのに」といってゲームを中断するのは子どもにとって一番やりたくないことです。
また、親から言われてやるのでは継続しにくいことが多く、かくれてこっそりゲームを始める、なんてことはよくある話です。
親子が話し合って納得できて子どもが守りやすいルールを作ることが有効です。
例えば、ゲームをやってもいいから勉強を30分でもやる、朝食・夕食は一緒に食べる、就寝時間を守る、などが挙げられます。
ゲーム以外の趣味を提案するという方も多いのではないでしょうか。
例えばスポーツやキャンプといったアウトドアのゲーム依存解消プログラムなどを良く目にします。
確かに様々な体験をすることは重要です。
しかし、趣味は本人が自発的に行うもの、それを通して楽しいと感じられて自己肯定感が上がることが重要で、親が強制的に提案するものは趣味にはなりません。
「たまには体を動かしてみない?」と誘ってみること自体は有効かもしれませんが、子どもが積極的ではないのに参加を促すことは逆効果になってしまうため、注意が必要です。
子どものゲーム依存を解消するためには、思春期はただでさえ親子関係にもつれが生じやすい時期です。
「やめなさい」「取り上げるよ」といった注意ばかりのコミュニケーションに陥りやすいです。
反抗的になるだけでなく、親子間のコミュニケーションも疎遠になりやすいです。
ゲームに関する話題で話しかけてみるのも一つの方法です。
ゲームのどのようなところが面白いのかといった話題をきっかけに、学校で困っていることや友人関係でうまくいっていないことを聞きだすことが有効です。
一緒にプレイしてみると「案外おもしろいし頭を使うんだ」という新しい気づきができるかもしれません。
ゲームに依存している子どもの場合、自己肯定感が低下していることが多いです。
学校の勉強についていけず、友人関係でうまくいっていない場合やゲーム以外の楽しみがなく、ストレス発散や不安を紛らわせている可能性もあります。
オンラインゲームの仲間が子どもにとっての居場所となっている可能性もあり、一概にゲームを取り上げるのは危険です。
子どもの自己肯定感をあげるために家事の手伝いを頼んでみるという方法もあります。
手伝ってくれた時には必ず感謝し、役に立っていることを伝えることが重要です。
親だけが抱え込むのではなく学校のスクールカウンセラーや都道府県の教育相談センター、医療機関に相談するという方法もあります。
子どもを連れていきづらい場合は、親だけが相談することも有効です。
ゲームに依存してしまう背景を根本的に解決していくことが大切です。親子で現状に向き合うことが大切です。
やる気アシストでは学校へ行くことができていないお子さんを多数任せていただいています。
不登校のお子さんは一人でいる時間がほかのお子さんよりも圧倒的に長くなり、必然的に孤独感を感じやすくなります。
また、お子さんが学校にいけないことで、勉強への不安やストレスを感じることもあるかと思います。高学年になってくると「勉強しなければ」という気持ちが強く、焦りや不安が募ってくるお子さんもいらっしゃいます。
アシストでは、このようなお子さんに寄り添い共感することでお子さんの孤独を回避しながら、お子さん1人ひとりにあった方法で少しずつ生活に勉強を取り入れていくところからスタートしていきます。
お子さんの勉強の習熟度に合わせたカリキュラムで「わかる」を引き出し自信や自己肯定感を高めていけるよう指導を行っていきます。勉強の習慣付けではお子さんの自主性を引き出すためにも、決して指示や過度なアドバイスはしません。
「できるところ」「得意なところ」から伸ばしていく指導で、達成感・充実感を感じてもらいながらお子さんが前に進めるようにそっとサポートをしていきます。
また、家庭教師の勉強法は、学校の授業のようにみんなが同じ内容を学習するというような指導ではなく、お子さんの様子を見ながら、分からない所・苦手・テストに出る箇所などお子さんにとって強化すべきポイントを集中学習することができるので、学校や塾に比べ、効率的に学習を進めていくことが可能です!
不登校の間、学校の勉強を両親が付きっ切りで見てあげたり、お子さんを面と向かって褒めるということはなかなか難しいというご家庭も多いです。家庭教師が間に入り、力になれることがあるかもしれません。不登校でお困りの方はまずはお気軽にご相談ください!


やる気アシストでは、ひきこもり支援相談士・不登校訪問専門員の認定資格を取得し、不登校のお子さんをより深く理解し、寄り添い、正しい知識を持って指導に当たれる体制づくりに力を入れています。
認定資格を持つスタッフが中心となり、社内スタッフや家庭教師に向け、不登校の正しい知識をつけるための勉強会や指導を行っています。
また、不登校のお子さんを持つご家族の方に向けても、接し方や声掛けの方法などをお伝えさせて頂いており、ご好評いただいております。
不登校のお子さんは第三者として接することができる家庭教師という存在が大きな役割を果たすことが多いです。私たちアシストは、正しい知識を持った家庭教師が、お子さんの「やる気」や「自信」を引き出しながら、勉強面だけでなく、精神面でもお子さんの良き相談相手になれるよう、お子さんに寄り添いながら指導を行っていきます。
体験授業では、同じようなお子さんを教えたことのある経験豊富なスタッフがお伺いして、ご家庭の要望やお子さんの希望をお聞きした上でぴったりの方法を一緒に考えていきます。
また、実際に指導が始まった後も気になることや心配なことがあれば、お電話にて専門スタッフが相談をお受けすることも可能です!
不登校は早期に対応することが大切です。具体的な質問や相談が無くても大丈夫!「不登校になってしまって不安…」といった曖昧なご相談でOK!
まずはお子さんのためにお早めにご相談ください!