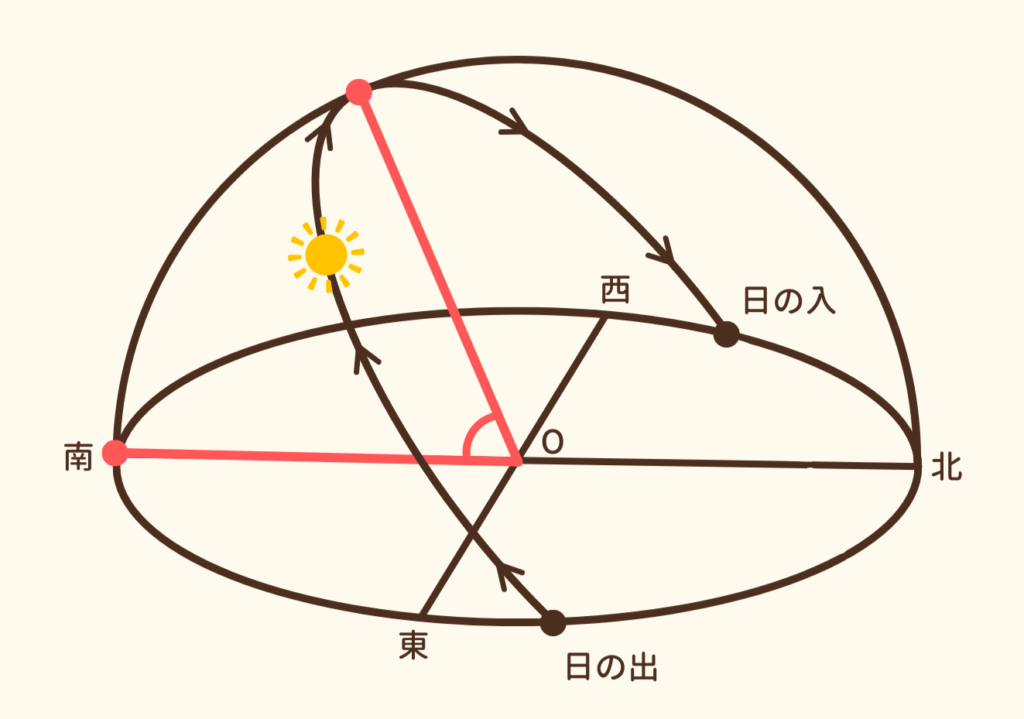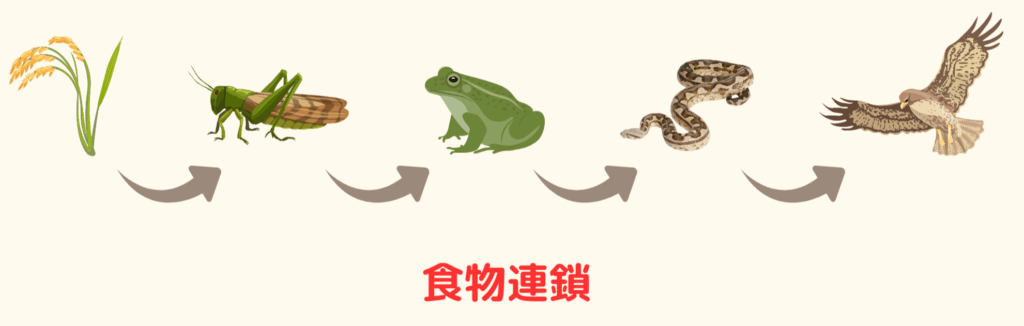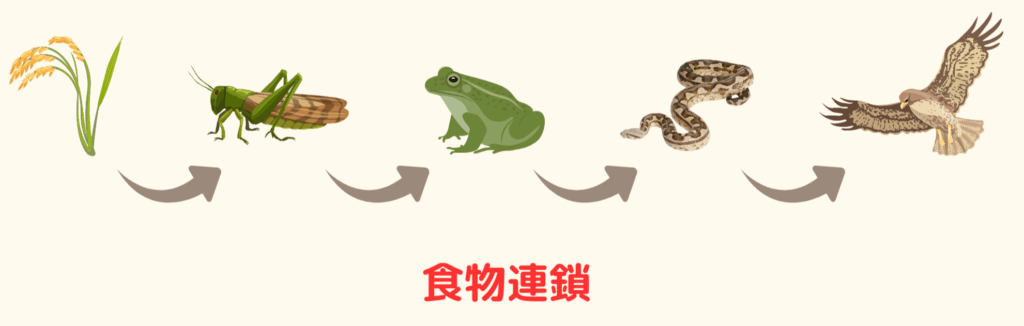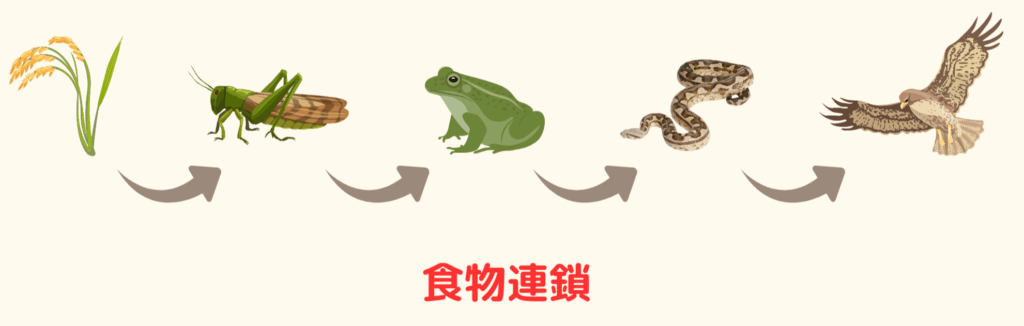戦国時代末期の三英傑と言えば、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康です。
織田信長は尾張の小さな土地から、一気に畿内を治め、天下統一の足掛かりを作りました。
その足掛かりを使って天下統一を成し遂げたのが豊臣秀吉でした!
しかし、この先の歴史を見ていくと、織田氏も豊臣氏も政治の表舞台に現れてこないです。
何故でしょうか?
それは、徳川家康という人物が虎視眈々と機会を伺って、現れたチャンスを逃さなかったからです!
さらにその徳川氏による盤石な政権が作られていきます。
今回は、その徳川家康と江戸幕府を開くまでについて解説していきます!
1542年、徳川家康は三河国の大名である松平家の息子として誕生します。
そのころの三河国というのはとっても弱く、現在の静岡県の大部分を支配していた今川氏に後ろ盾となってもらっていました。
いわゆる主従関係があったのです。
そこで、当時の家康(その頃は竹千代と呼ばれていた)は今川氏の人質として駿河に送られてしまいます。
異郷の地で過ごすこと、何と12年。
1561年に今川義元が桶狭間の戦いで討死したことで、やっと三河の国に戻ることが出来たのでした。
三河の地に戻ると、早速、織田信長と同盟を結ぶこととなります。
今川氏はその頃には敵対関係となっており、家康にとって脅威となっていました。
また、信長としても美濃国との敵対関係があり、互いの利害が一致したのでした。
そこから、主に現在の愛知県東部、静岡県西部の辺りの戦いにおいて、織田信長と共に戦うことがありました(三方ヶ原の戦いや長篠の戦いは有名ですね)。
このようにして織田信長は着々と天下統一の足掛かりを作っていき、家康は遠江国(静岡県西部)まで勢力を伸ばしていきました。
そんな中、織田信長が本能寺にて暗殺されてしまいます。これによって同盟関係は終わります。
織田信長が亡くなった後、天下を取りに行ったのが羽柴秀吉でした。
織田信長が持っていた領地の多くを支配下に置いた秀吉は、同じく織田信長の家臣で領地の多くを支配下に置いた柴田氏と対立しました。
秀吉はそれを退けると、柴田氏が押さえていた領地も含む広大な領地を手に入れました。
ところが、全部の領地ではないのです。
ゴタゴタしている間に家康が北に領地を拡大し、かなりの勢力を持つまでになったのです。
そして、家康は秀吉に対して臣従する姿勢は見せるものの、ある程度距離も置いていました。
そんな中で、起こったのが信長の息子・家康 vs 秀吉の小牧・長久手の戦いでした。
家康と秀吉はこの戦いで和解することとなり、家康が「秀吉の次に実権がある」ことを秀吉に認めさせたうえで、正式に従属することを認めます。
そして、秀吉は天下統一を成し遂げた後、1598年に亡くなるのです。
豊臣家のナンバーワンが亡くなると、豊臣家の家督(家柄のトップ)は豊臣秀頼となりました。
ただし、秀頼の年はそのときわずか6才。
そんな中、家康は大名としては豊臣秀吉の次に力がありましたので、家康は一気に天下を取ろうと画策します。
そこで立ちふさがったのが石田三成です。
石田三成は家康の勢力拡大を嫌い、畿内の征伐を行なったり、家康が当時政治を行っていた伏見城を攻撃したりしました。
このとき家康は福島の方へ征伐に行っていたのですが、それをきくと西に引き返していきます。
こうして衝突したのが、現在の岐阜県と滋賀県の県境である関ヶ原であり、その地名からこの戦いを関ヶ原の戦いといいます。
この戦いはわずか1日で徳川家康側の勝利に終わり、家康の支配力が確実なものとなります。
\小・中・高校生の勉強にお悩みのある方へ/
関ヶ原の戦いが終わり、抵抗勢力がいなくなったので、徳川家康が本格的に政治の実権を握ることとなります。
1603年には徳川家康は朝廷より征夷大将軍に任命され、現在の東京に江戸幕府が開かれました。
江戸に幕府が置かれた理由は、家康の支配の拠点が江戸城だったからです。
朝廷に認められて幕府が開かれ、日本を統一した支配者となったわけですが、まだ権力を細やかながら保持しているものがいました。
それは豊臣家です。
豊臣家を大坂城から追い出すことで、天下統一の総仕上げと考えていたのでしょう。
家康は、大阪を1614年の冬と1615年の夏に攻撃します。
これを大坂冬の陣、大坂夏の陣といいます。
ここで陣とか聞いたことの無い言葉を使っていますが、今までの戦いと何ら変わりません。
夏の陣にて豊臣秀頼、秀頼の母である淀殿は自刃し、豊臣秀吉の血は途絶えることにより、天下統一は完全なものとなりました。
これを成し遂げた翌年の1616年にその生涯を終えることとなります。
こうして徳川家康が開いた江戸幕府は約260年という長期間に渡って続きます。
江戸時代は戦乱が極端に少なく(戦国時代が多すぎたのですが)、平和な時代だったので、様々な文化が花開きました。
また、政治的にも安定した体制を作ったり、外国との交流について制約をして国のアイデンティティーが築かれるなど、大変興味深い時代になります。
この辺の話は別の記事で解説しますね!