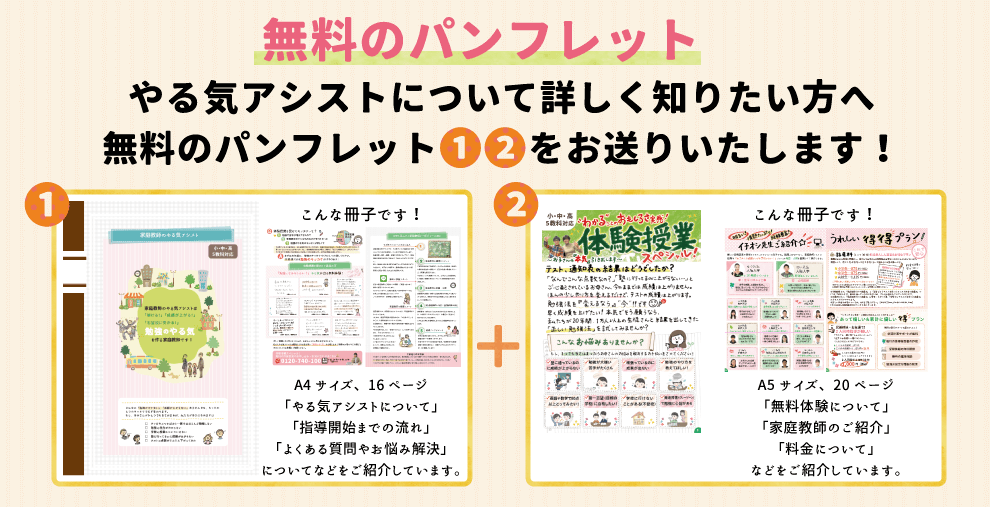家庭教師のやる気アシストへの学年別指導方法。小学校1年生のお子さんへの教え方を紹介します。
小学校1年生はどんなことを学ぶのか、アシストではどのような指導・サポートができるのかを紹介していきたいと思います。
文部科学省『生きる力』
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/
小学校1年生は全教科の中で国語を一番多く学びます。また、理科や社会を学ばずに生活科として学ぶことも特徴の一つです。
国語ではひらがなの読み書きに一番時間をかけて学びます。鉛筆の持ち方から「とめ・はね・はらえ」などの基本的な文字の書き方を学んでいきます。他にも読み聞かせや音読など、文章と触れる機会を取っていきます。
算数では数の構成、数の表し方、たし算、ひき算などを学びます。まずは、1から10、さらに11から20、そして21から100までの数を学びます。たし算とひき算では文章問題も出てくるので、算数の勉強だけじゃなく、国語の勉強も大切になってきます。
| 区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 |
| 算数 | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 理科 | 0 | 0 | 90 | 105 | 105 | 105 |
| 社会 | 0 | 0 | 70 | 90 | 100 | 105 |
| 生活 | 102 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音楽 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 図画工作 | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 家庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 55 |
| 体育 | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 |
| 道徳 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 外国語 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 総合 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 特別活動 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 総授業数 | 850 | 910 | 945 | 980 | 980 | 980 |
国語のつまずきポイントは、「長音・促音・拗音の使い分け」「助詞の使い分け」「主語と述語との関係」の3点です。具体的に見ていきましょう!
話し言葉よりも書き言葉で間違えやすいです。
例えば、「おとうさん」を「おとおさん」と書いたり、「かってください」を「かてください」と書いたりしてしまうことがよくあります。
助詞とは、「は」「へ」「を」などを意味します。
「わたしは学校へ行って、友達をつくりました」など文章を組み立てるときに重要な要素になっています。
助詞も最初は正しく使い分けるのは難しいです。最初は、「わたしわ」「学校え」などひらがなと間違えてしまうこともあります。
また慣れないうちは、助詞が抜けてしまったり、間違った助詞を使ってしまうことも多いつまづきポイントです。
「桃太郎が鬼退治をした」など、主語と述語との関係を理解することも難しいポイントの一つです。
完璧ではなくても、「〇〇が〜した」をしっかり相手に伝えられるようにしましょう。
国語力だけでなく、コミュニケーション力を上げるためには、主語と述語の関係を理解しておくことが大切になってきます。
算数のつまずきポイントは、「繰り上がりのある足し算」「繰り下がりのある引き算」「時刻の読み方」の3点です。
「6+8」「12+7」などです。
繰り上がりがあると、両手だけでは計算ができなくなってしまうので、数の概念を理解できていないと難しく思えてしまいます。身近なブロックやおはじきなどを使って教えてあげるといいかもしれません。
「15-7」「17-9」などです。
このときは、10のまとまりをしっかり理解できるかどうかが大事です。
例えば、15-7なら、
というステップになります。ひっ算を学べば楽になるのですが、1年生のうちに概念から学ぶことに意味があります。
時計を見て時刻を読むことも、よくつまづくポイントです。
長い針と短い針を別々に見て、考えることは難しいので、理解するまでに時間がかかります。
時刻の読み方をどれだけ早く理解できるかは、生活の中でどれだけ時刻を読む経験をしたかが重要です。
小学校1年生の勉強、国語と算数で大事になってくることは、「しっかりと対話・会話を行うこと」だとアシストは考えます。
たとえば、国語は書き言葉はもちろん、話し言葉にもつまずきのポイントが隠れていますし、何よりも文章に触れることが第一です。算数に関しても、時刻は時計を見ながら、会話して言葉と映像を結びつける作業が大事になってくると思います。
昨今、映像授業やプリントなどが主流になりつつありますが、完全な1対1の指導ができる家庭教師だからこそ、これから小中高と12年間続いていく教育の一番の基本の一年間を有意義なものにできると考えています。