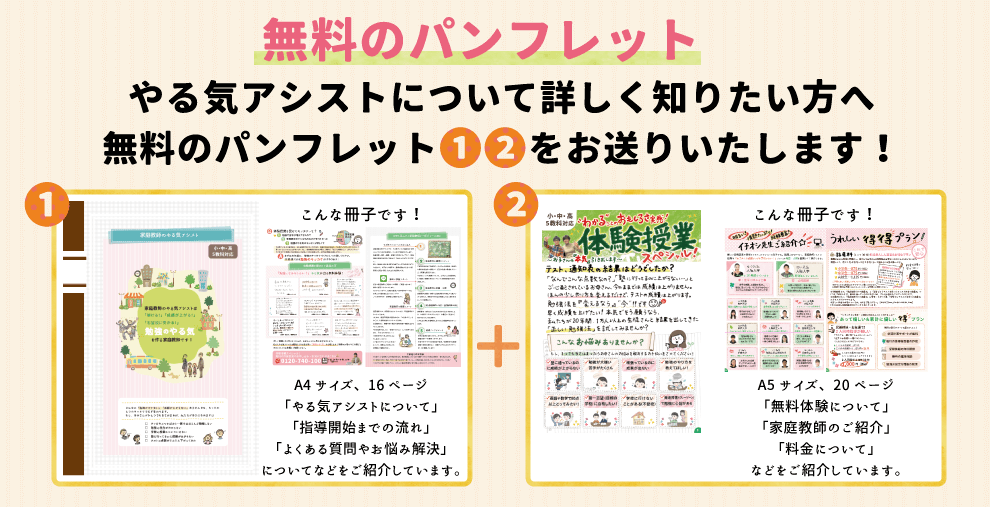家庭教師のやる気アシストへの学年別指導方法。中学校1年生のお子さんへの教え方を紹介します。
中学校1年生はどんなことを学ぶのか、アシストではどのような指導・サポートができるのかを紹介していきたいと思います。
文部科学省『生きる力』
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/
中学校1年生は全教科の中で英語・数学・国語を一番多く学びます。中学校1年生はこれからの3年間の基礎となる1年間なので、主要3科目はしっかりと押さえておきましょう。また、中学校3年間は割り振りが変わるだけで、トータルの時間数は変わらないこともポイントです。
英語ではbe動詞や一般動詞、助動詞や疑問詞、過去形や未来形などを学んでいきます。実は学ぶ単元数自体は平成28年よりも減っています。どういうことは下で詳しく説明していきます。
数学では数の正と負、方程式、平面図形や空間図形、比例、反比例の理解を深めます。具体的には7つの単元を学んでいきます。そのうち4つのジャンルに分けれるので、下で詳しく説明していきます。
国語では316字の新出漢字に加えて、説明文・随筆分・物語文を学んでいきます。国語は3年間を通して内容の変化はあまりないので、中学校1年生で勉強法を掴んでおくと、安定した成績を出すことができます。
| 区分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 140 | 140 | 105 |
| 社会 | 105 | 105 | 140 |
| 数学 | 140 | 105 | 140 |
| 理科 | 105 | 140 | 140 |
| 音楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 外国語 | 140 | 140 | 140 |
| 道徳 | 35 | 35 | 35 |
| 総合 | 50 | 70 | 70 |
| 特別活動 | 35 | 35 | 35 |
| 総授業数 | 1015 | 1015 | 1015 |
これは中学校英語全体に言えることですが、中学の英語のレベルは以前に比べて格段に上がりました。理由としては、英語を小学校5年生から学び始めるようになったからです。
実際、文部科学省が公開している、中学校卒業する時点での単語レベルは、1200語レベルだったのに対し、現在は2200~2500語レベルになっています。
ところが、中学校1年生だけ見ると、単元数は減っていますね。これは学ぶ項目が減ったというよりも、 「1つの項目ごとに学ぶ内容がギュッと詰まった」といえます。
特に1年生の単元でつまずきやすい分野は、「三単現」と「過去形」かなと思います。どちらも動詞の変化や、疑問文の作り方などをしっかり理解しないといけません。そのためにはbe動詞をしっかりと理解して、英語に慣れておく必要があります。
1年生の数学は主に以下の4つのジャンルに分けることができると言えます。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
「正の数・負の数」の単元がこのジャンルに当てはまります。
ここでは数学ではじめて登場する「マイナス」という数字の概念、プラスとマイナスを混ぜた式の四則演算、指数・絶対値といった数学特有の表現方法など多岐にわたります。ここを理解すればのちのち登場する方程式や関数、さらには統計学の基礎まで幅広く対応することができます。
代数学とは、簡単に言うとxやyといった文字で量を表して、求めていくことです。
「文字の式」・「方程式」・「変化と対応」の単元がこのジャンルに当てはまります。
代数学は中学2年生になっても3年生になっても登場する数学のジャンルです。1年生のうちに押さえておきましょう。
幾何学とは、簡単に言うと図形問題のことです。
「平面図形」・「空間図形」の単元がこのジャンルに当てはまります。
幾何学を勉強するときは、コンパスや三角定規を忘れずに持参するようにしましょう!小学校からの延長部分なので不安な人は復習をしておくとよいです。
統計学とは、簡単に言うとデータの整理のことです。
「資料の活用」の単元がこのジャンルに当てはまります。
中学1年生の数学では、データの分布を上手にとるための度数分布、ヒストグラム、メジアンなどを学習します。
一口に読解問題といっていもジャンルによってコツが変わってきます。
上で紹介したこの3つのジャンルに分けることができます。
説明文では、使われている単語が専門用語の場合、読むだけで意味が分からないという生徒さんが多いです。
しかし、実は説明文は作者が気付いたり発見した新しいことを読者に伝えるために書かれている文章なので、どんなに単語が難しく、書かれている文章が回りくどくても、「作者の主張」さえ発見できれば簡単なのです。
作者の主張は文章を通して一貫していますので、何度も出てくる言葉や主張にアンダーラインを引くことで、作者の主張を把握できます。
随筆文はエッセイとも呼ばれ、あるがままを作者の思いのままに綴った文章のことです。
文章の構成さえ理解できれば、あとは段落の内容が「事実」なのか、「作者の意見」なのかを確認すれば問題を解くことができます。
一貫性があるようで内容が捉えきれない随筆文を苦手とする生徒さんが多いですが、この分離法をマスターすれば、随筆文攻略も簡単です。
物語文には必ず主人公が存在します。
その主人公を軸にして物語が展開され、問題の構成も主人公を基盤にするので、主人公の心情等を問う問題が複数題必ず出てきます。
主人公の心情という漠然とした問いに戸惑って苦手意識を持つ生徒さんが多くみられますが、その場合は主人公の行動や心情が書かれている文章に印やアンダーラインを引いてしっかり整理することで、主人公の気持ちを掴むことができます。
中学校1年生の勉強で大事になってくることは、「小学生から卒業すること」だとアシストは考えます。
授業時間や科目、定期テストなど、小学校との違い、いわゆる「中1ギャップ」に悩まされる生徒さんが多いです。中1の勉強をスムーズに進めるためには、何より授業を大切にし、しっかり理解することが一番です。そして、授業をしっかり理解するには、予習・復習を習慣にすることが重要です。
昨今、映像授業やプリントなどが主流になりつつありますが、完全な1対1の指導ができる家庭教師だからこそ、中学校3年間の基礎となる、中学校1年生を有意義なものにできると考えています。